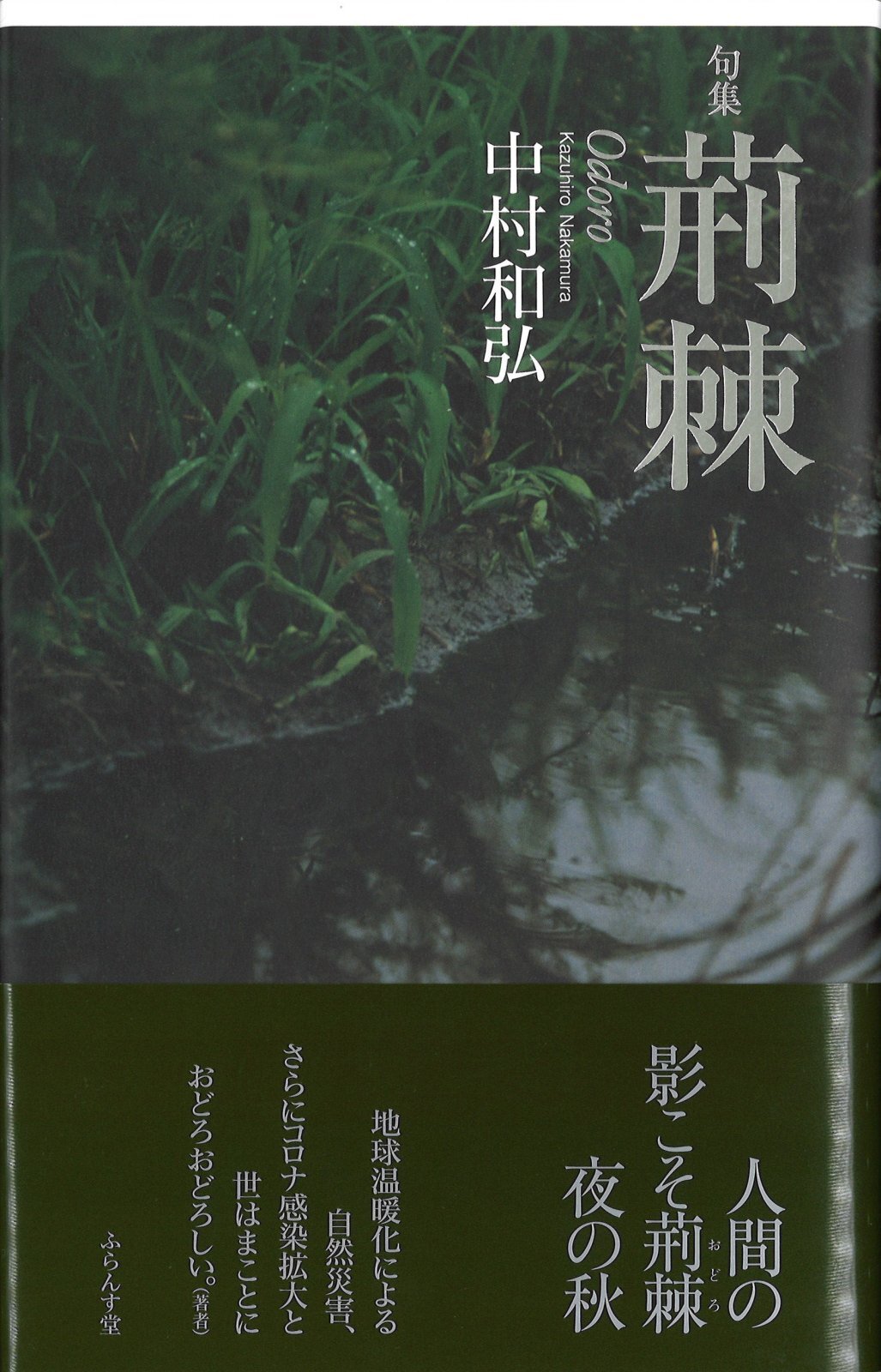「大坂の俳句―明治編」を読む 俳人・村上鞆彦が読む『大阪の俳句』シリーズ vol.42016.6.29
水落露石『露石句集』を読む vol.4

正岡子規が蕪村に注目し、その作品を称揚したことは、広く知られている。当時の子規一門は、埋もれようとしていた蕪村の作品の掘り起こしとその研究とに熱心だったという。
水落露石(明治五年・一八七二年生まれ)もそんな一人として、蕪村に深く傾倒した。今回の『露石句集』を読んでいてまず目につくのも、蕪村調とでも言うべき典雅で彩りのある句、またゆったりとした情緒が懐かしさを誘う句であった。
大牡丹崩れむとして今日もあり
大輪の牡丹。盛りを過ぎて花弁が毀れようとするのを、一線で押し止めている。その姿には危うい状況ならではの美が宿る。それを感得し、大らかながら引き締まった声調で詠っている。この牡丹が一片二片と花弁を落とし始めると今度は〈牡丹散て打かさなりぬ二三片 蕪村〉の崩れの美を見せることになる。
つゝじ折りて安居の僧が下山哉
行を終えた僧が、山から下りてくる。手には一本のつつじ。その可憐な花は、僧の好もしい風雅の心の現れである。麓の里には久し振りに会いたい知人もいよう。そんな人懐かしさの心に、つつじが一点の色を添える。
春風や堤を通る傀儡師
春風に吹かれながら、旅の傀儡師が長い堤を通ってゆく。広やかな川辺の風景とうららかな日差し。この句を読んでいると〈春風や堤長うして家遠し〉〈遅き日のつもりて遠きむかしかな〉という遠いものへの懐かしさを詠った蕪村の句を思い出す。露石の「傀儡師」もまた、かつて見た光景の回想、もしくは遠い時代の空想であったのかもしれない。
蕪村は各地を遍歴したのち京都に腰を据えた。大阪在住の露石も京都に頻繁に足を向けた。後年には京都へ居を移しもしている。そんな地縁の繋がりもあって、露石は蕪村に深く傾倒したのかもしれない。
京へ寄せる露石の情は余程強かったようで、京の風物を詠った句も数多く残されている。
葵かけて横顔青き舎人かな
京の花大方散りて壬生念仏
一句目は葵祭。冠に懸けた葵の葉の影が、うっすらと青く、舎人に扮した男の横顔に映っている。匂いたつような凛々しい横顔が想像される。二句目の壬生念仏は晩春の行事。無言の仮面劇と、緩やかで素朴な囃子が有名である。その響きに過ぎ行く春を惜しみ、大方散ってしまった京の花を惜しむ。二句共に京の伝統行事が美しく詠み取られている。
春の夜や湯槽の人の京言葉
明治三十四年、東京の花を愛でた後に逗留した箱根での作。ちょうど湯に居合わせた人が京言葉をつかった。それを聞くにつけ、しばらく留守にしている京のことが恋しく思われる。露石の京への愛着は、なかなかに深いのである。
さて、露石の事績として記憶に止めておきたいものに「京阪満月会」がある。これは露石、寒川鼠骨、中川四明の三人が中心となって明治二十九年に結成された句会である。当時の子規の日本派は、東京と松山とに一つずつ句会があるきりであった。「京阪満月会」の結成は、後に隆盛を見せる関西俳壇の黎明を告げる出来事であった。
村山古郷の『明治俳壇史』には、その最初の会合の折の興味深い逸事が記載されている。
最後に小柄で色の白い二十六、七歳の瀟洒な紳士が、黒い背広を着た人を伴って到着した。大阪の水落露石と、従兄の武富瓦全であった。露石は席に就くと、隣の人に、今まで木屋町で芸者をあげて遊んで来たなどと話した。
若くして小間物問屋の当主であった露石は、なかなかの粋人、その道の遊びにも深く通じていた様子が窺える。
水楼や風はらみたる青簾
楼の灯や夏山迫る京の町
稲妻や更けてぞ語る蚊帳の中
颯爽とした青簾、情緒の濃い楼閣のともしび、艶めいた蚊帳の睦言。こういった句からもそのひととなりの一面が垣間見えよう。
不自由のない境遇による洗練された美意識と、蕪村に倣った情感豊かで駘蕩とした句風。水落露石も また、関西俳壇の礎を築くのに大きく貢献した一人であったことを深く実感させられる、今回の『露石句集』である。
●筆者紹介
村上鞆彦(むらかみ・ともひこ)
昭和54年8月2日、大分県生まれ。中学の頃、友人の勧めにより俳句を始める。大学進学とともに、鷲谷七菜子主宰の「南風」に入会。以前から<滝となる前のしづけさ藤映す 七菜子>の一句に憧れていた。その後、南風新人賞・南風賞を受賞し、現在、山上樹実雄のもとで同人として勉強中。俳人協会会員。