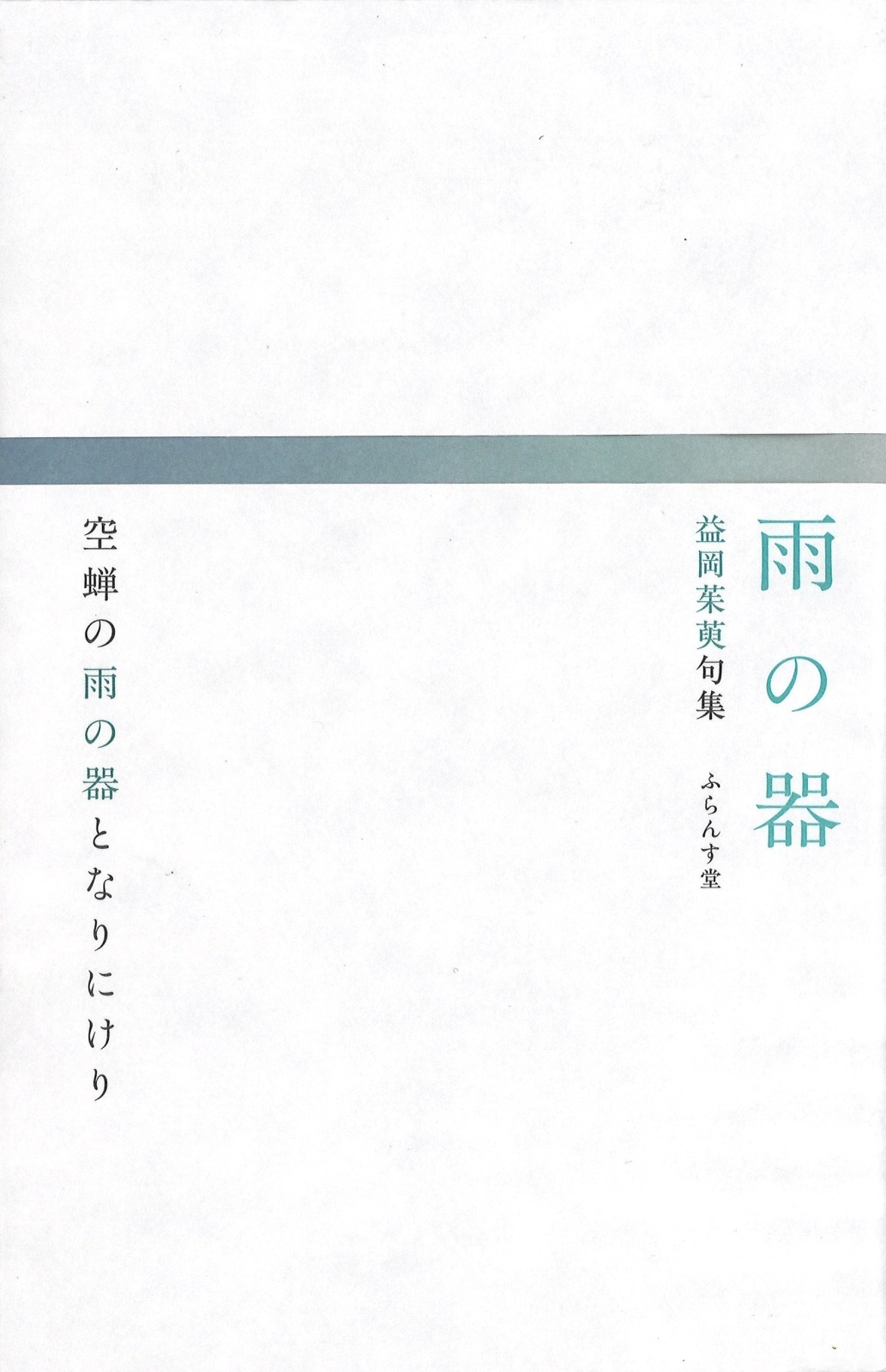「大坂の俳句―明治編」を読む 俳人・村上鞆彦が読む『大阪の俳句』シリーズ vol.32016.6.29
相島虚吼『虚吼句集』を読む vol.3

相島虚吼の『虚吼句集』は昭和七年に刊行された。その「はしがき」には、数多くの作品から厳選したことが記されている。更にそこから、今井妙子氏が五〇一句を抄出し、今回の『虚吼句集』は編まれた。
相島虚吼は、慶応三年(一八六七)、茨城県に生まれた。この慶応三年という年には、文学や学問の上に大きな足跡を残した人物がたくさん生まれている。夏目漱石、幸田露伴、斎藤緑雨、宮武外骨、尾崎紅葉、南方熊楠といった面々である。そのなかに、後に虚吼と深く交わることになった正岡子規もいた。
今井妙子氏の「解説」に引用された記事や略年譜によると、子規と虚吼とが初めて出会ったのは、明治二十八年(一八九五)、日本へ向けて航行中の船上でのことだった。二人共、戦役従軍記者として平壌や旅順などを取材し、日本へ帰還するところだった。
その船中で、長旅の疲れからか子規は喀血してしまうが、虚吼の手助けにより、無事に神戸病院へ入院することが出来た、とも伝えられている。共に従軍記者に志願するような勇ましさを持ち、加えて同い年の生まれとくれば、二人の間に互いの意気に感じるといった強い結びつきが生まれても当然であろう。
この出会いを切っ掛けに、虚吼は俳句を詠むようになった。
虚吼は子規と出会った後、高浜虚子とも交流を持ち、「ホトトギス」に参加したので、その句風は客観写生が基となっている。
勝鶏の眼に一点の血潮かな
羅のすべり落ちたる衣桁かな
花氷かすかにけぶりとけ行けり
一句目、闘鶏に勝っていまだ興奮の収まらぬ鶏の眼に、一点の血潮を見出した。この血潮から、激しかった勝負の様子や勝鶏の厳しい面構えなどが想像される。二句目、「すべり落ちたる」という一瞬の動きから、羅の匂うばかりの艶やかさが立ちのぼる。三句目、かすかな「けぶり」の発見によって、溶けてゆく氷の質感と涼味が、ありありと表現された。三句共、凝視を効かせて、素材を高い精度で把握した句である。
一方で、大きな景を大らかな気息で詠んだ句も捨て難い。
富士八合目
銀漢の流るゝ音を聴かんかな
秋出水見ゆる限りの月夜かな
降る雪の中へ太陽出でにけり
いずれの句も、大景が湛えた深い静謐さが印象的である。
しかしこれまでに見たような句は、虚吼の作風のある一面でしかない。残りの大部分を占めて、虚吼の面目を躍如とさせているのは、自在な滑稽味が生きた句である。
放屁虫貯へもなく放ちけり
シャンペンのキルク弾ねたる桜かな
燎原の火もへらゝゝとなりにけり
一句目、「貯へもなく」という自嘲の表現が「放屁虫」と相俟って、哀感と表裏一体の可笑しみを醸し出している。二句目、カタカナの軽い調子が生きた、リズミカルな明るさがある。三句目、「へらゝゝ」の擬態語が巧み。盛んな野焼の様を見て昂っていた心も、火の衰えと共にいつしか萎んでしまったのだろう。
虚吼の死後、昭和十一年に刊行された『相島虚吼句集』には、虚子が次のような序文を寄せている。
此作者は溜飲の下がる男であつて、小理屈など云はず、めそゝゝせず、しめつぽい処のない、然し其実人情に厚い、わけ知りだと云ふ感じのする男である。
この言葉は虚吼の人物だけでなく、その句風の特徴をも的確に言い留めている。
ところで、この『虚吼句集』を読んでいると、柿が登場する句がいくつもあることに気づく。一部を抽くと、
初めての接木の柿がつげにけり
咽喉痛む我に食ませよ蜂屋柿
金剛山
法師この次来れば柿甘し
柿といえば、子規である。子規は柿を好んで食し、また柿の句を多く遺した。そんな柿を詠むことで、虚吼は志半ばで若くして逝った同年生まれの友を追慕していたのではなかっただろうか。
はじめに触れた面々については、坪内祐三著『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(2001・マガジンハウス)に詳しい。虚吼もまた、一つの枠に収まらぬ“旋毛曲り”のバイタリティーで、俳句だけでなく、新聞界や政治の世界でも大きな活躍を遂げた人だった。
●筆者紹介
村上鞆彦(むらかみ・ともひこ)
昭和54年8月2日、大分県生まれ。中学の頃、友人の勧めにより俳句を始める。大学進学とともに、鷲谷七菜子主宰の「南風」に入会。以前から<滝となる前のしづけさ藤映す 七菜子>の一句に憧れていた。その後、南風新人賞・南風賞を受賞し、現在、山上樹実雄のもとで同人として勉強中。俳人協会会員。