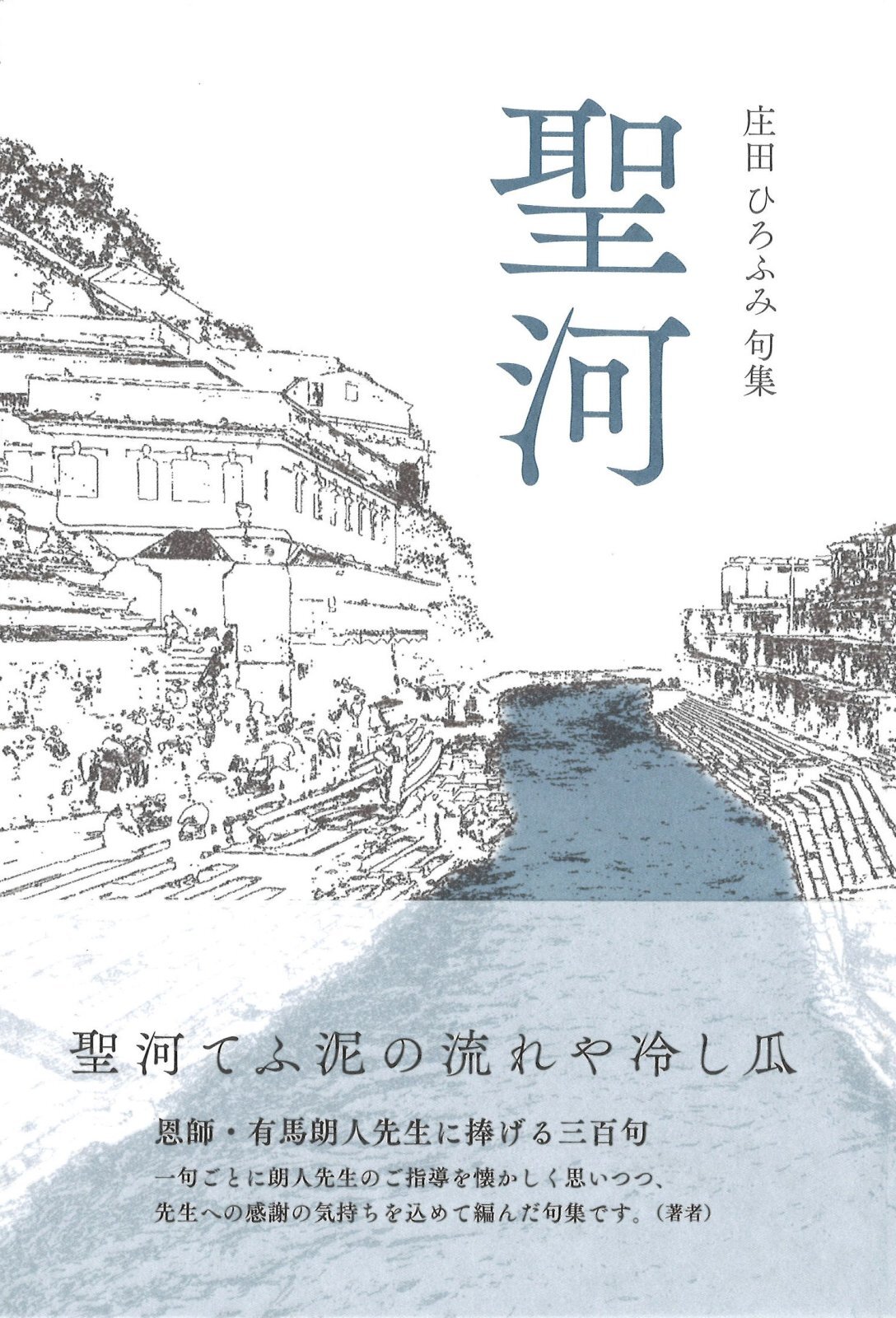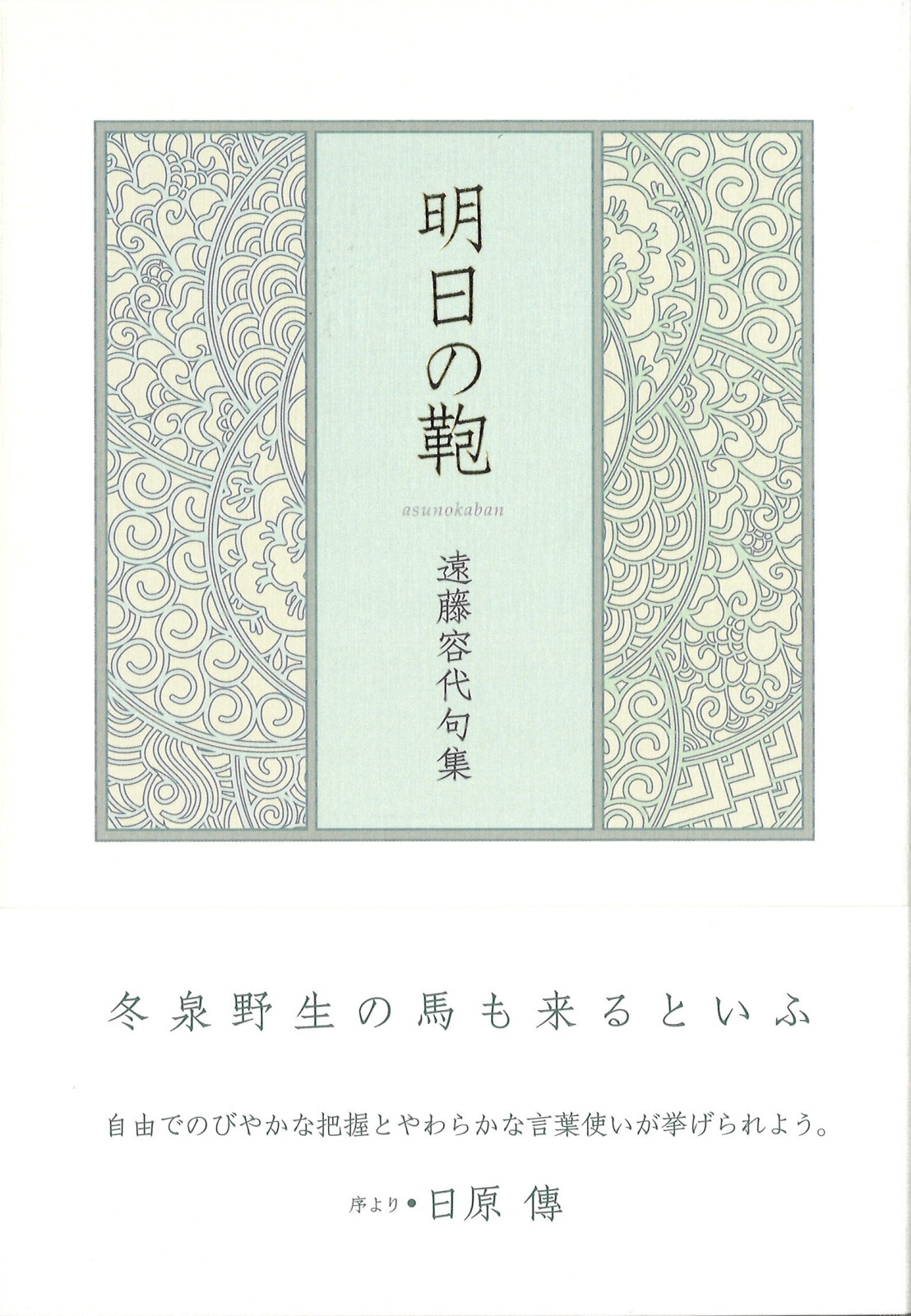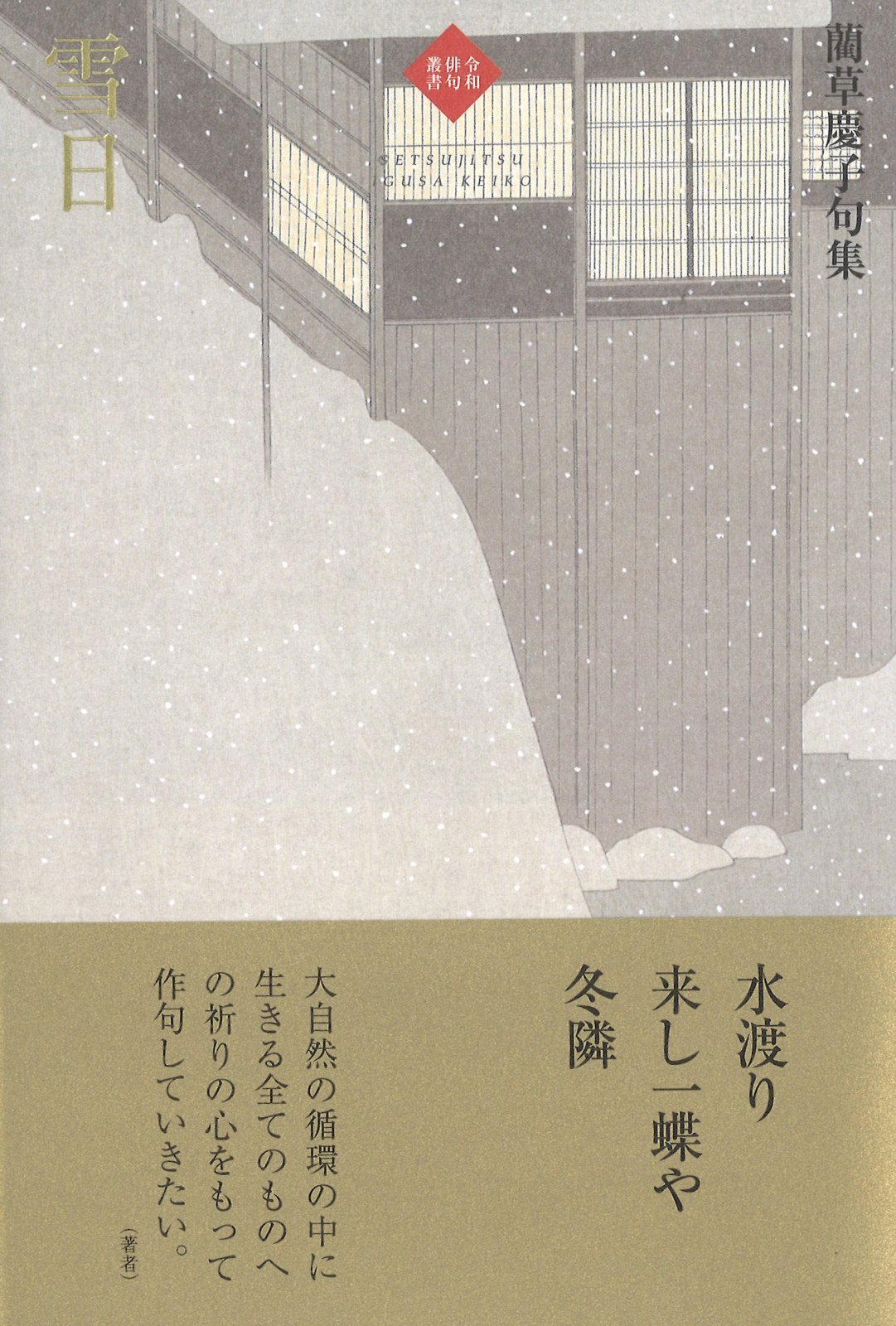「大坂の俳句―明治編」を読む 俳人・村上鞆彦が読む『大阪の俳句』シリーズ vol.22016.6.29
芦田秋窓句集『草紅葉抄』を読む

句集『草紅葉』が刊行されたのは昭和五年、芦田秋窓四八歳の折である。そこから約五〇〇句を安達しげを氏が抄出して、今回の句集『草紅葉抄』は編まれている。
秋窓は俳句だけではなく、俳画も能くした。「現代俳画の鼻祖」「今様蕪村」などとも称されたという。安達氏の「解説」によれば、秋窓が俳画に志したきっかけは、子規の俳画に触発されたことにあるそうである。ただし、子規の俳画に大いに感心して、自分も絵筆を、と思ったわけではなかった。実はその逆で、大いに不満を覚えたのである。その子規の俳画とは、寒牡丹の絵に寒牡丹の句を配した、いわゆる「ベタ付け」のもの。日ごろから子規の俳句理念に深く傾倒し、子規を生涯の師と仰いでいた秋窓でも、流石にこの垢抜けのしない俳画は受け入れることが出来なかった。そして、それを発奮材料として新たに俳画への志を立てた。もともと秋窓の胸中には画への興味関心が育っていたのであり、それは筆墨を商う家に生まれたという環境の影響でもあっただろう。
『秋窓・指月両師遺墨集』(平成一〇年、白扇社刊。なお、平成一二年には同じく白扇社から『続刊』が刊行されている)により秋窓の俳画を見てみると、やはり「ベタ付け」を拒絶した人だけに、句の内容と画とは不即不離の関係で、絶妙のバランスを保っている。そして、筆遣いには俳画ならではの省略が効いており、簡潔に明快に風景や素材が描かれている。そんな得意の絵筆を揮っている秋窓の姿が彷彿とする句を挙げてみよう。
陽炎や草の汁にてものを書く
羽織の裏に絵を望まれぬ宵の春
妓の扇とつて酔筆ふるひけり
襖の画一気に描きぬ汗落つる
画をかくに裸になつてしまひけり
秋窓は多作であり、生涯に数万点の俳画を描いたとも言われている。時には、絵の具のかわりに春の若草の汁を用いてみたり、また羽織や扇・襖などにも描いたりと、その作品の形態も多種多様であった。妓と興じては酔筆をふるい、暑さ極まっては着物を脱いでまで制作に没頭する、俳画に心遊ばせている秋窓の闊達な姿が浮かび上がってくる。
俳画について、秋窓は次のような言葉を残している。
俳画は描くものの意志が表示されたらよいのだ。ただ技巧的の上手さより無技巧の純真さと稚拙が生命で、微塵の嫌味があってはいけない。 (「白扇」昭和二七年九月号)
この言葉は、秋窓俳句の特色をもよく物語っている。彼の句は、技巧に凝るよりも淡々とした大らかな気息を尊ぶ風が色濃く、気負わず粘らず、微塵の嫌味も感じさせないのである。そんな佳吟のいくつかを紹介したい。
友禅を干せる磧や春の雪
とりどりの色彩が賑やかに息づいている。雪は降っているが、もう冬ではない春の明るい情感が一句を包む。〈鶺鴒や山をうつして水蒼き〉という句もあり、こちらは単色で静謐さを湛えた山の色が鮮やかにイメージされる。
牧牛に暖き日となりにけり
いかにも悠々とした穏やかな春の眺めである。このような清閑な心持ちで日常生活に目を遣れば、〈朝粥の味十月となりにけり〉といった滋味深い句が生まれてくる。
流連の昼を読書や青簾
青簾の「青」という語感が、主人公の年齢の若さを思わせる。その世代特有の物憂さや昼の遊里のもの寂しさも漂っていよう。秋窓には〈酒の座へ浴衣に更へて来りけり〉など、酒やそれにまつわる句も多く、その左党振りが偲ばれる。〈描き終へし襖を見つゝ麦酒かな〉、満足のいった仕事のあとの一杯はまた格別である。
鼻かんで耳がつまりぬ冬籠
とぼけた味わいのユーモラスな句も散見される。〈かゝり凧とるべきすべも尽きにけり〉〈雛段につかへて開かぬ襖かな〉。純真さや稚気をよしとする心が生んだ滑稽句に、思わず口元が綻ぶ。
俳句と併せて画を学び、俳画の道を志そうという人は、今も昔も、そう多くはないようである。その意味で、秋窓は俳句史のなかでも一種特異な立場の作家と言える。この『草紅葉抄』により、秋窓の句とその事跡とが、より多くの方の目に留まることが望まれてならない。
●筆者紹介
村上鞆彦(むらかみ・ともひこ)
昭和54年8月2日、大分県生まれ。中学の頃、友人の勧めにより俳句を始める。大学進学とともに、鷲谷七菜子主宰の「南風」に入会。以前から<滝となる前のしづけさ藤映す 七菜子>の一句に憧れていた。その後、南風新人賞・南風賞を受賞し、現在、山上樹実雄のもとで同人として勉強中。俳人協会会員。