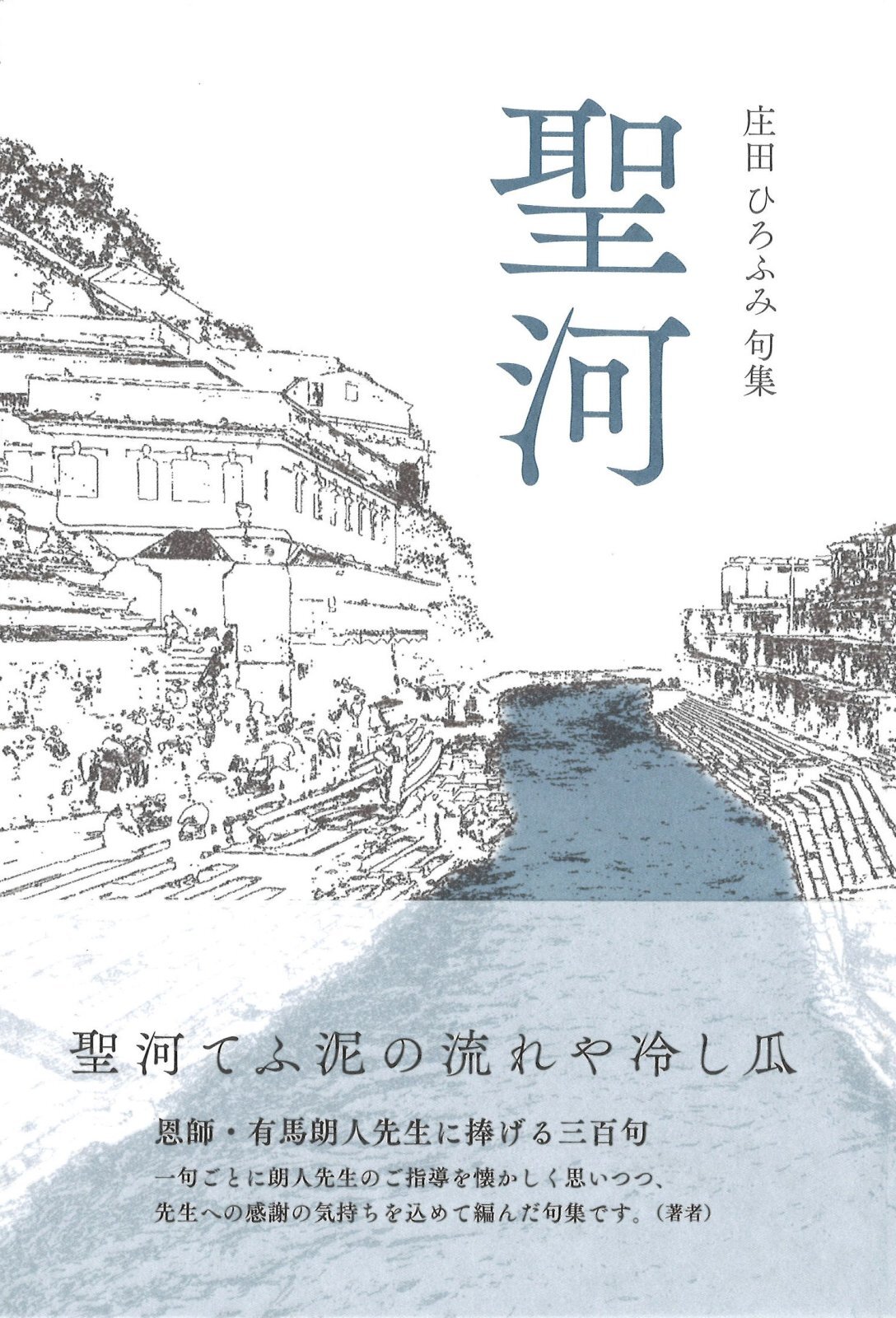「大坂の俳句―明治編」を読む 俳人・村上鞆彦が読む『大阪の俳句』シリーズ vol.52016.6.29
永田青嵐『永田青嵐句集』を読む

永田青嵐は明治九年兵庫県に生まれた。京都の第三高等学校に入学後、寒川鼠骨を識って俳句を始め、京阪満月会で活躍した。
今回の『永田青嵐句集』は、収録作品を明治期製作のものに限っている。その意図を、編者のわたなべじゅんこ氏は「青嵐の俳句人生の起点」を考え、「初期作品を改めて見直す契機」にしたかったと解説に述べている。
蚊や蠅や蚤や虱や子や孫や
集中、最も驚かされた句がこれである。「鬱陶しいもの、煩わしいもの」を並べ立てるという趣向だろう。蚊、蠅、蚤、虱、なるほどここまでは納得がゆくが、続けて唐突に子と孫とが出てくる。これには一瞬わが目を疑ってしまった。しかし当然ながら、これは愛情の逆説表現である。煩わしいと言いながらも、内心には子や孫への愛惜の思いが深く湛えられているのである。
かくてあるべきにあらねば畠打つ
主人公は、鬱勃たる意志に促されて決然と腰を上げた若者だろう。しかし世間に打って出て理念を訴えるといった大仰なことではなく、「畠打つ」という土に根差した営みを選択する。上五・中七の詰屈とした厳しい調子から、一転して「畠打つ」へと転じたその落差に、自然と滑稽味が生まれている。
ふんばるよ串の螽のふんばるよ
串焼きの螽を詠んで「ふんばるよ」「ふんばるよ」とは、まさに童心の屈託のなさが捉えた大きな発見と言える。どこか稚拙さを感じさせる調子も、却ってここでは活きている。「ふんばるよ」とは言いながら、すでに串に焼かれた螽である点に一抹の哀れがこもる。
このように一種型破りとでも言うべき自由闊達な詠み振りが印象深い青嵐であるが、ほかにも大景を明瞭なタッチで描いた叙景句や細やかな情感のこもった身辺詠に佳句が多い。
春の海白帆蓬莱より来る
引潮や陽炎燃ゆる蟹の甲
鶏頭に日の残りけり勝手口
一句目、「蓬莱より」で一気に奥行きが展けた。空想による浪漫的な味わいもある。二句目、蟹の甲羅に焦点を当てながら、干潟の春の陽気が遺憾なく描かれている。三句目、残照の鶏頭を通して、一日が平穏に終わってゆくことへの安堵感が伝わる。「勝手口」であることで、懐かしい生活の匂いが備わった。
ところで、今回の『永田青嵐句集』には、随筆「俳諧懺悔」が併録されている。これは後年の青嵐が俳句にまつわる思い出を語ったものだが、その中にある次の一節が興味深い。
「私は如何に贔屓目に見ても俳句の天才では無い、唯平凡の横好きである。(略)私の程度の俳句ならば普通の人ならば誰にでも出来る。之を余技として楽しむには面白いものである。凡そ余技は下手な程仕合せである」。
「下手な程仕合せ」とあっけらかんと言ってのけるところに、青嵐の人となりの一端が垣間見えよう。しかし実際の作品を窺う限り、一角の俳人たるべき才は有していた青嵐である。それがなぜ自らを見限り、俳句を余技と割り切ってしまったのかというと、それは子規や虚子、碧梧桐、鼠骨と交際することで、その並々ならぬ力量に直に触れてしまったことが原因している。「俳諧懺悔」には次のようにある。「私は自ら公平に考えて見て迚も是等の人の様な天才が無い。之が天才家の真似をして居ては、鵜の真似する烏の如く水に溺れる外は無い」。
この決断によって青嵐は俳人としての大成の芽を自ら摘んでしまった。しかし官吏永田秀次郎としては、これが大きな道を歩む機縁となった。俳句で立つことを諦め勉学一本に打ち込んで高等学校を卒業した彼は、各地の警察部長を務めた後、県知事や貴族院議員を経て、ついには東京市長、拓務大臣、鉄道大臣と要職を歴任したのである。
この成功の背景には、もちろん職務上の有能さがあったことだろうが、それ以上に彼の人間性に因る部分が大きかったのではないか。この『永田青嵐句集』を読むと、すでに若い頃から、拘りのない大らかさと飾らぬ素朴さを持っていた青嵐の人間像が浮かび上がってくる。
畑打のうしろに遠き都かな
京に居て花の弥生を貧乏なり
旅の耻は柿喰ひつゝ歩みけり
なお付言すると、大正十二年に関東大震災が起こった時、青嵐は東京市長をつとめていた。彼は被災民の救援と復興事業に尽力し、名市長と讃えられたということである。
●筆者紹介
村上鞆彦(むらかみ・ともひこ)
昭和54年8月2日、大分県生まれ。中学の頃、友人の勧めにより俳句を始める。大学進学とともに、鷲谷七菜子主宰の「南風」に入会。以前から<滝となる前のしづけさ藤映す 七菜子>の一句に憧れていた。その後、南風新人賞・南風賞を受賞し、現在、山上樹実雄のもとで同人として勉強中。俳人協会会員。