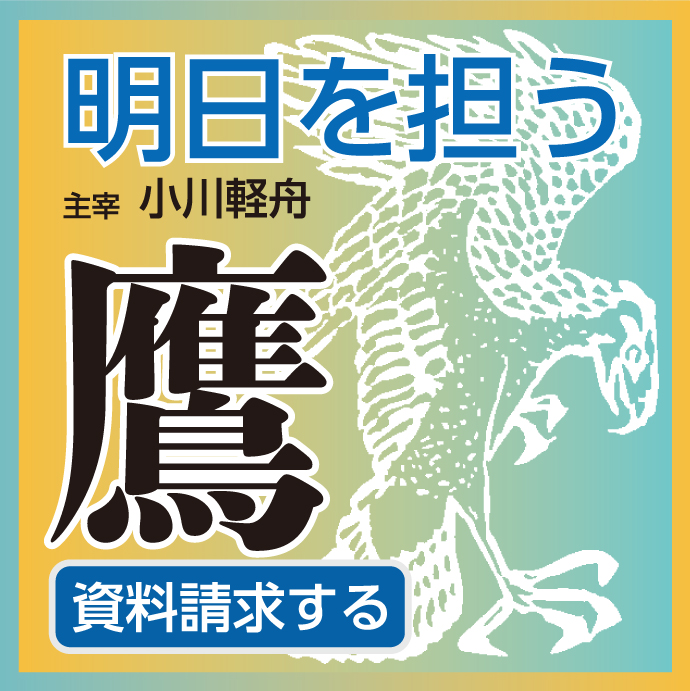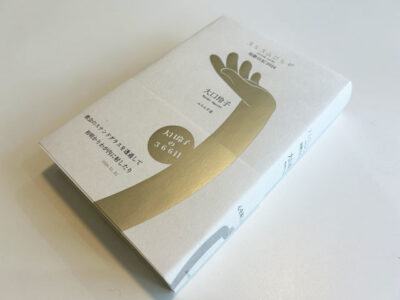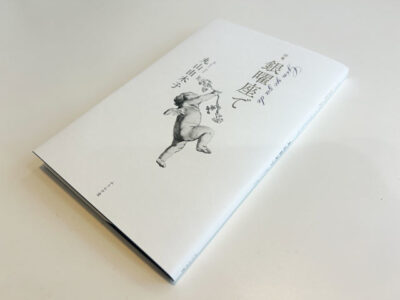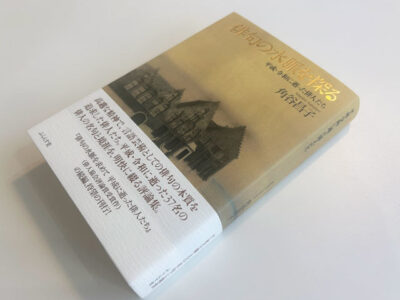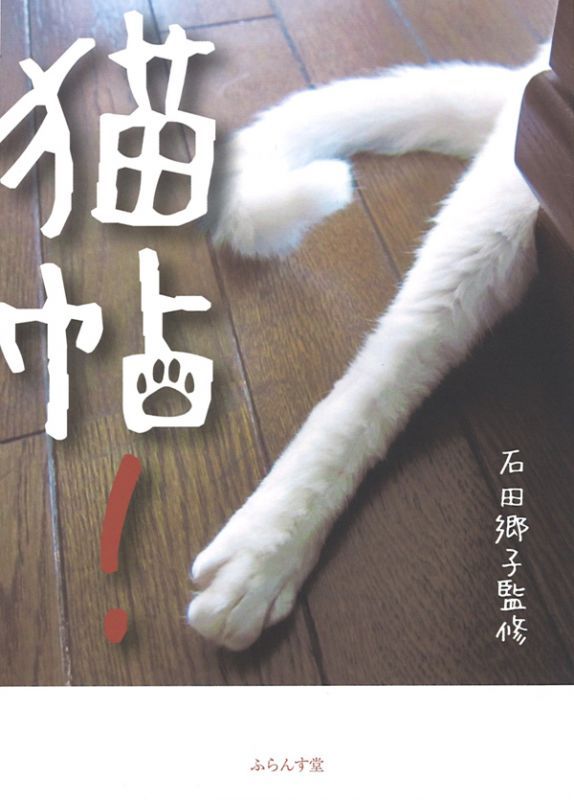七夕まつり
第24回俳句四季大賞2025.7.7

選考委員の皆さん、お集まりいただいた方々、ありがとうございました。今日は誠に珍しい日でございます。七夕であり、令和7年7月7日と、ラッキー7が三つ揃っています。天皇陛下が変わらないと叶わないという日であり、誠に光栄で忘れられないように思います。日本で初めて「俳句」と「映像」というのを結びつけて考えたひとは、寺田寅彦です。明治の時代に「映像と俳句はよく似てる」と言っています。寺田寅彦は夏目漱石の弟子ですが、それ以上に大変優れた科学者でした。数々の先見的な研究をしています。その一つに「俳句はモンタージュである」と寺田は結論として言っています。俳句モンタージュ論ですね。松本俊夫の『映像の発見』という本があります。副題に「アヴァンギャルドとドキュメンタリー」と書かれています。この中で「映像作家で優れたひとたちは皆ドキュメンタリストである」とドキュメンタリーというものをしっかりと把握するというか、それが優れた作家の努力なんだと書いてあります。著者の松本さんは海外で数々のドキュメンタリーの賞をとっている大変優れた映像作家です。僕はこの本を自分の作句の参考にしています。すぐれたドキュメンタリストは結果的に言うとアヴァンギャルド、前衛的なんだと言っています。俳句はいま全世界で作られています。私はしばしば目を通していますが、大変レベルが上がってきています。そういった作品のベースはドキュメンタリーだと思います。たとえば、ウクライナの俳人の作品を見ると分かります。いまがどういう状態なのか、彼らが訴えている。それは表現としてはドキュメンタリーなんですね。アメリカや中国の作家もそうです。ドキュメンタリーの把握が広がってきているように思います。日本は、伝統の踏襲だけが重要であるかのようですが、それは大事ではあるけれど、その中に閉じこもっている時代は尽きてきている、他のレベルが上がってきている。ひょっとすると世界の賞をとるのは海外の俳人になるかもしれないとも思います。俳句は芭蕉の時代からドキュメンタリーの要素を持っています。当時は「ドキュメンタリー」という言葉がなかったから、そういう批評はだれもしていないというだけで、よく見てみると、芭蕉の「おくのほそ道」はドキュメンタリーです。世界には共通したテーマがたくさん増えています。戦争だけの問題じゃない。異常気象の問題、自然破壊の問題もあります。それを無関心でいられるかということも踏まえて、俳句を考えるという時期に入ってきている、我々俳人としてもしっかり受け止めて自分の作品にしていかなくてはいけないと思います。それが物を作る、表現する表現者の責任と、そんなことを思います。そんなことも含めて私の乏しい能力、努力を含めて、コツコツとやってきました。この賞をはじめいくつかの賞をいただけたということは私にとっても大変節目になりました。ありがとうございました。

また、第25「俳句四季」全国俳句大会の授賞式も行われ、その後、蜂谷一人さんによる、「動画的俳句論」の講演が文字通り動画を交えて行われました。この日のために用意された「俳句表現における動画」のスペシャル公演は大好評でした。
(ふらんす堂「編集日記」2025/7/8より抜粋/Yamaoka Kimiko)