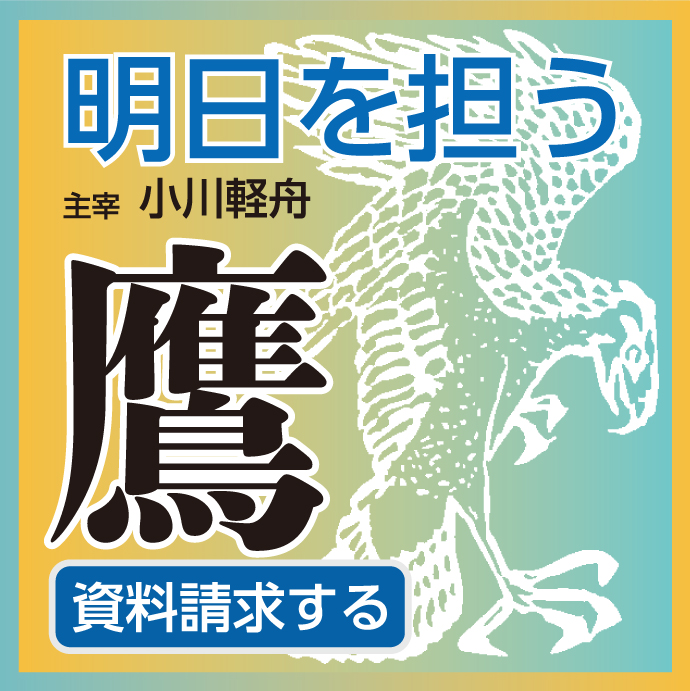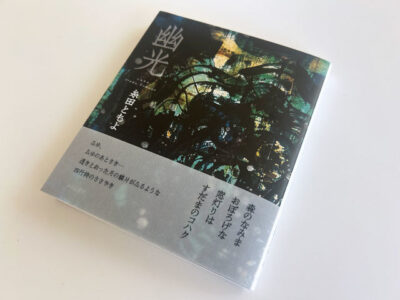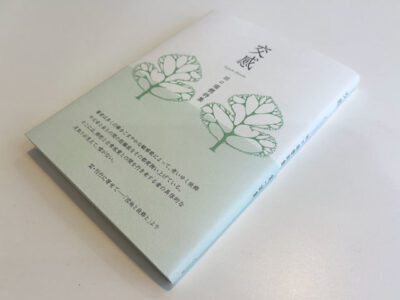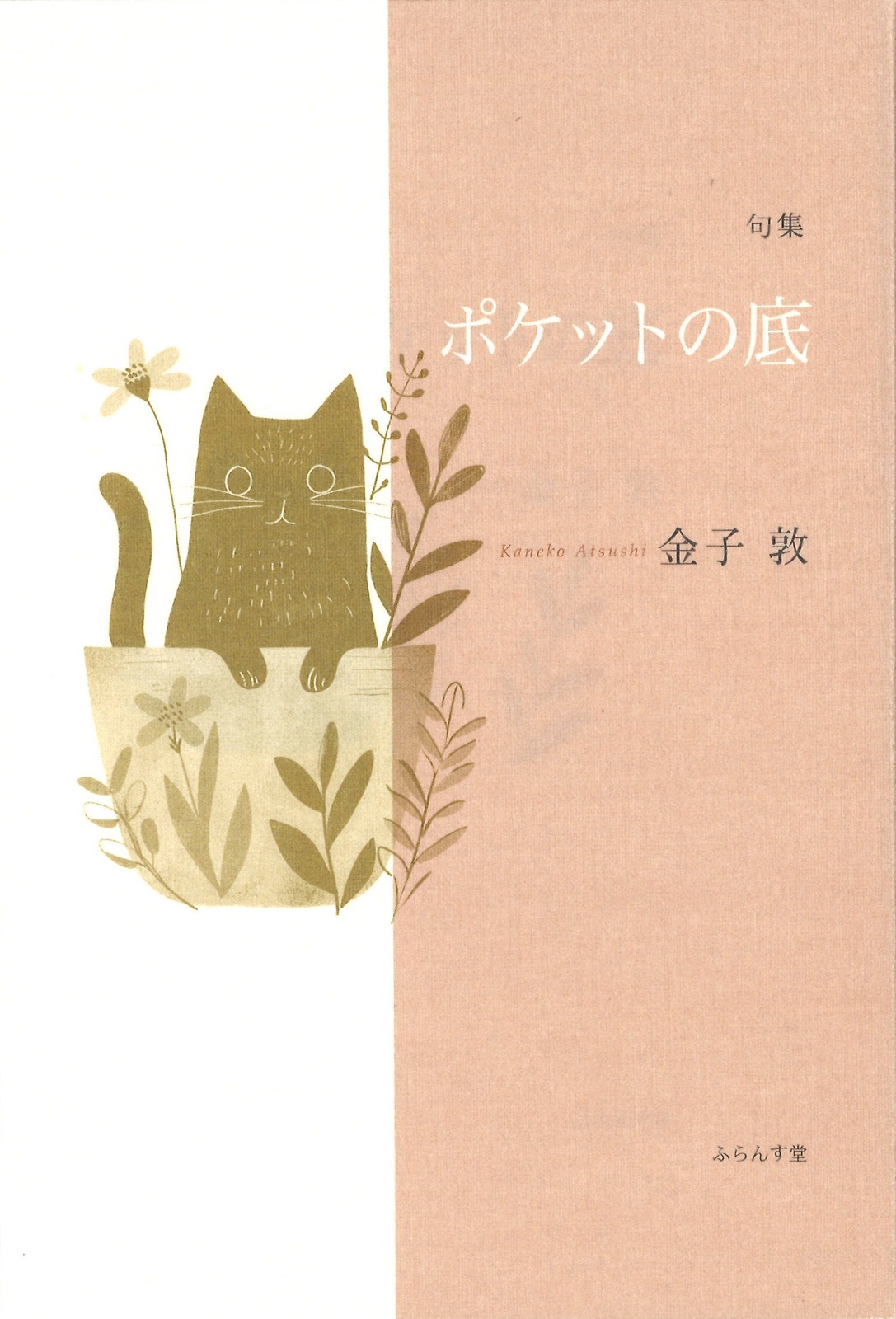岸本尚毅の吟行日記72016.6.30
俳句実践講座
岸本尚毅さんが指導をされている句会を取材しています。
実践の場で俳句をどうつくるか、大変参考になると思います。
●岸本尚毅作
大いなる木の葉や水の上に反り
焼藷の煙よく見え木の葉降り
銭の音させて一人や焼藷屋
見えてゐる水底清き落葉かな
てのひらに載る生きものや冬近し
昼の日のかくも斜めや草の花
●岸本尚毅特選
石の階狭くて紅葉散らばれるり 定生
神無月をしかたまりて鹿の子は 喜代子
後ろ手にあるじ戻り来日短か みよ
草木みな風にしたがふ秋の暮 八江
いまだゐる藪蚊を打ちて冬仕度 紀子
朝の雀夕べの烏冬めける 八江
森深く短日の池深みどり しげ子
返り花苑の時報のやや遅れ 紀子
囲ひして狸と狐となりあふ 喜代子
末枯れて艶やかな実が茎の先 定生
冬めくや高みに松の緑ある 章
残る蠅小さき水の玉吸うて とも
●尚毅選
藁屑のそこらに散つて日短 八江
末枯れてつややかな葉でありにけり 定生
吹く風のなき黄落でありにけり 定生
噴水の小さくなりて冬に入る 喜代子
水真中動かぬ魚や石蕗の花 とも
落語家のやうに茶を飲む文化の日 章
石蕗咲いて縁側の日に読みふける 八江
鶴の嘴落葉突き刺し歩むなり 紀子
リヤカーの落葉の上の箕と箒 定生
猿山に喧嘩無き日や菊日和 章
戸袋のあたりさつぱり萩刈られ 八江
草葎なかに直ぐなる泡立草 紀子
逝く秋の縦横にある象の皺 紀子
思うやうにボート進まず日短 とも
草幹おほひつくす苔かな鶏皮 夢
晴れてくるところみるみる鰯雲 昌子
●岸本尚毅氏の講評

○石の階狭くて紅葉散らばれる
「狭い」っていうのが確かなんですね。狭いところにわりあい密に紅葉が散らばっているという風景というのは確かにあるなあと思います。
○神無月をしかたまりて鹿の子は
「神無月」が効いているように思えます。爽波先生の句で「鮠(はや)の子のかたまりが濃し年の暮」だったと思いますが、「かたまりが濃し」というのもいいと思ったんですが、この「をしかたまりて」というのもいい表現だと思います。

○後ろ手にあるじ戻り来日短か
このちょっと出かけてというのが、「短日」という季語と合うと思います。
○草木みな風にしたがふ秋の暮
これはまあ、ちょっとなんでもないようなんだけど、「風にしたがふ」という表現はなかなかうまくいかないのですが、この句の場合は「秋の暮」とうまくなじんでいるのではないでしょうか。
○森深く短日の池深みどり
これはいいですね。森の中の池の様がすんなりと表現されているんじゃないでしょうか。
○返り花苑の時報のやや遅れ
これも捨てがたい句ですね。「返り花」がよく効いてますね。
○冬めくや高みに松の緑ある
こふっとこう見上げたときに松の緑が目にはいったという、そのふとした感じが上手いと思いました。
○朝の雀夕べの烏冬めけ
こういう対句の句っていうのはつくりやすいっていうことはありますね。うまくいけばいいのですが、私自身もときどき作るんですが、ちょっとくずしたほうが 言い場合もあるんですね。あんまりきっちり対句になっていると言葉のほうが調子がよすぎてしまい、くずした方がいいというケースがたまにはあります。
○末枯れてつややかな葉でありにけり
○吹く風のなき黄落でありにけり
「吹く風がなくて黄落」とか「末枯れてつややか」とかちょっと反対のベクトルのものを組合せることがあるのですが、この作者の場合表現が非常にさりげない ので反対のベクトルを組合せているということをあんまり目立たせずにすっと読ませてしまうところが上手いなあと思いますね。
●おことわり
このページは、俳句愛好者の作句の勉強の一助とする目的で、岸本尚毅さんが句友諸氏と個人的に行っている句会の様子を紹介させて頂くものです。この句会は 私的な会であり、部外者には一切オープンにされておりません。そのため日付・場所・作者名は非公開です。お問い合わせはご遠慮ください。引用された作品の 著作権は、実在する各作品の作者に帰属しますのでご注意ください。