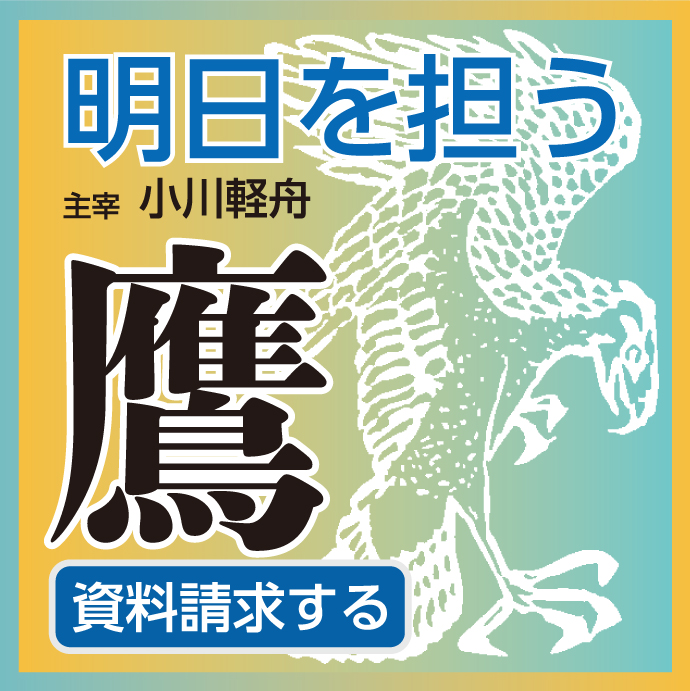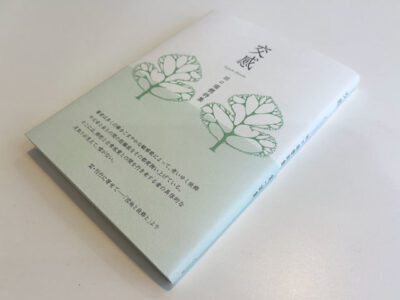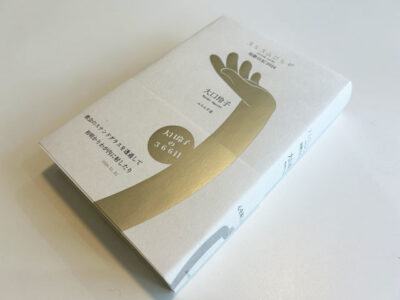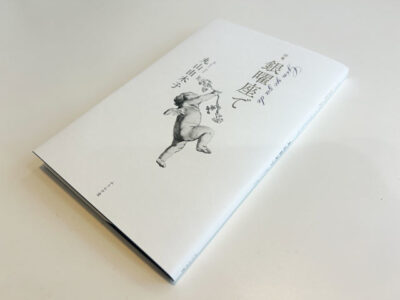第62回現代俳句全国大会2025.11.3


今日は珍しく秋晴れで、いかにも晩秋の空という感じになりました。そして、池之端の破れ蓮も美しいですね。私は蓮が好きなので、池の端を一周しました。季節の蓮池の様子、これをぐるりと回って観察すると面白いです。今年の夏は暑かったですが、青々として蓮池は元気でした。そんな佳き日にまったく思いがけなく、受賞の知らせをいただいて嬉しさの反面狼狽えておりました。気が小さいので褒められると狼狽える性格で、あまり表彰されることに慣れていません。でも皆さんにお目にかかれて嬉しく思います。今日は立ち見席もあって盛況ですね。これも現俳協の幹事や、青年部のスタッフのおかげですね。若い人たちが現俳協を盛り上げつつあってありがたいことだなと思います。50歳以下の若手が多いのは現代俳句協会であります。私の師は田川飛旅子先生ですが、私が俳句に興味を持ったのは30代に入った頃でした。俳句は老人の趣味だと思っていました。俳句に惹かれて俳句をしたわけではなく、裏千家のお茶を習っていた時に、俳句の会に誘われたのがきっかけでした。最初は面白くなく、しぶしぶ出ていたのですが、2年くらいしたら田川先生がいらっしゃったんですね。先生はキリスト教の熱心な信者でもあり、人間が大変優しく、芯が太い方でした。大変繊細なところをもっていて、その先生の作品に惹かれました。「僕の先生で素晴らしい先生がいるから来い」と田川先生から言われ、寒雷の加藤楸邨先生にも合わせていただきました。私の財産です。そのころから俳句を真剣にやり始めました。「陸」という結社と現代俳句協会の幹事をしておりました。こういった団体に所属することで緊張感を持てたと思います。サボることができないというありがたさ。現俳協で何かを引き受ければ、またそれも緊張感が生まれます。ここまで保つことができたのは、結社、団体であると思います。いいメンバーにも恵まれました。とても充実していると思います。このような皆さんに推されるというのはとても嬉しく、狼狽えつつ、ありがたく思います。これからも私に何かできることがあれば、頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。

僕は昔から賞は時の運と、選考委員に恵まれるとことと思っています。今回の受賞も選考委員に恵まれたと思います。僕の句集は書評しにくいという評判があるようで、今回も黙殺に近かったこの句集をよく掬い上げてくださったと思います。唯一、鬣TATEGAMI賞で評価をいただいておりました。それに加えて今回、80回目の現代俳句協会賞をいただけて嬉しかったです。80回という節目、昭和80年、戦後100年という節目にいただけたのは、神の思し召しにありがたさを感じています。いただけたときは実感があまりなかったのですが、今日は嬉しいです。また、受賞をすると、周りのひとが喜んでくださるんですね。それが本当に嬉しくおもいました。いろんな人にお世話になって生きてきました。「俳句空間」をやって5年目で仕事もやめました。また連載にもちょうど飽きてきた頃に。林桂さんがやっていた、「詩学」という雑誌で、仕事を辞めた僕に対して「大井恒行にはまだ俳人としての仕事が残っている」と言ってくれたことに励まされました。坪内稔典さんが、俳句は「生まれたばかりでまだ変わりうる詩形だ」と言っていました。今の俳句は有機定型のオンパレードですが、俳句はそれだけではないと伝えていきたいと思います。成り行きの人生でしたが、成り行きの最後にこの賞に恵まれたように思います。今日は本当にありがとうございました。

私は約29年前に慶應大学に留学した時、金子兜太先生に師事して俳句を勉強し始めました。仕事が忙しくなって中断したこともありましたが2018年に兜太先生が亡くなって、翌年、先生に言われた言葉を思い出して再開しました。今は「海原」に所属しながら、中日文化交流の場として「聊楽句会」という超結社の句会も50人ぐらいでやっています。『静涵』は、自らの内面と向き合いながら、日常の襞や季節の揺らぎに耳をすませ、一語一語の言葉を掬い取るようにして紡いだ句集です。題名の通り、静かに涵(うるお)うということを願い、派手な技巧や声高な主張ではなく、余白と沈黙に託されたものを大切にしたい、という思いを持って作り続けてまいりました。そのような一冊を今回ご評価いただけたことは、何よりの励みであり、同時に大きな責任も感じております。昨年度の協会賞受賞者であるマブソン青眼氏が、「外国人が日本語で俳句は作れないと未だに思っている人もいるようです。この受賞で世の中の理解が少しでも進めばいい」と語られたことが、強く印象に残っております。私もまた、その言葉に深く共感いたしております。俳句は日本語という言語に根差した詩形でありながら、その内奥にある感性や精神は、国や文化の壁を越えて届きうるものと信じております。だからこそ、表現の手段としての日本語に真摯な敬意を払いながら、他者と自然、そして自己の在り方を十七音に託していきたいと考えております。今回の受賞が、俳句の可能性がさらに広がり、また、より多くの人に開かれた場となるための一つの契機として捉えております。

今度の句集は自分にとっては最後の句集になると思っていました。76歳です。もうこれが最後だわと思っていたのですが、この賞をいただけることが本当に嬉しく思っています。選考委員の方々にもひとりひとり御礼を申し上げたいです。私の先生である宇佐美魚目先生が陰で見守ってくださっているような気がしてきました。句集の表紙には魚目先生の句も使わせていただきました。俳句を作るとき、先生の真似をしようとか、いいところをとろうとかを思ったことがなく、好き勝手に作っていました。そういう意味では先生の弟子とは言えませんが、それでも続けてこられたのは先生のおかげです。今度先生のお墓にお参りしようと思います。ありがとうございました。

第45回現代俳句評論賞受賞・元木幸一、第26回現代俳句協会年度作品賞・なつはづき、水口圭子、第42回兜太現代俳句賞新人賞・百瀬一兎の皆さま。



(ふらんす堂「編集日記」2025/11/4より抜粋/Yamaoka Kimiko)