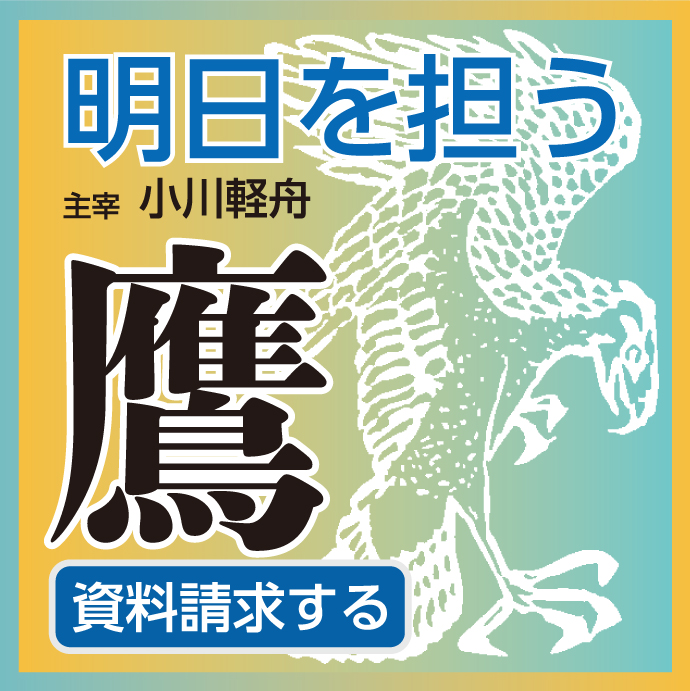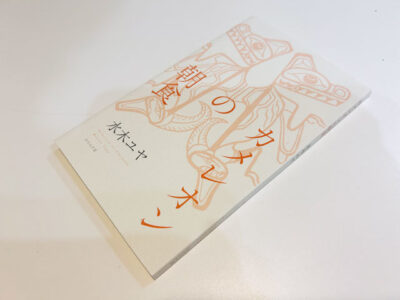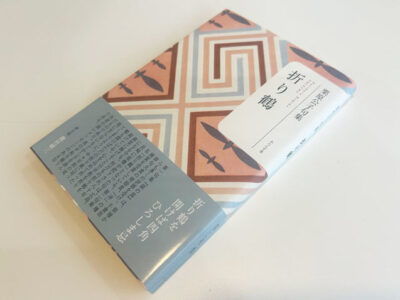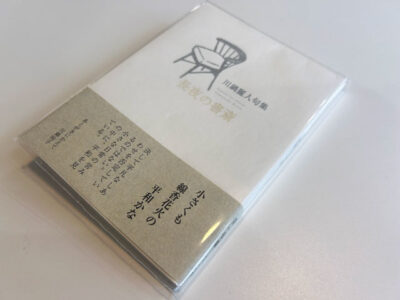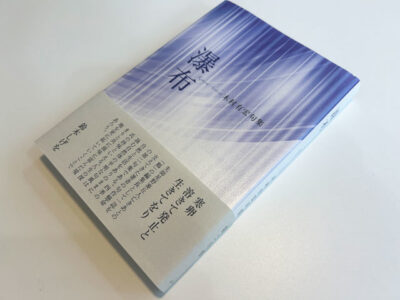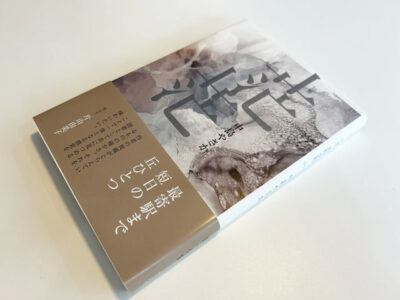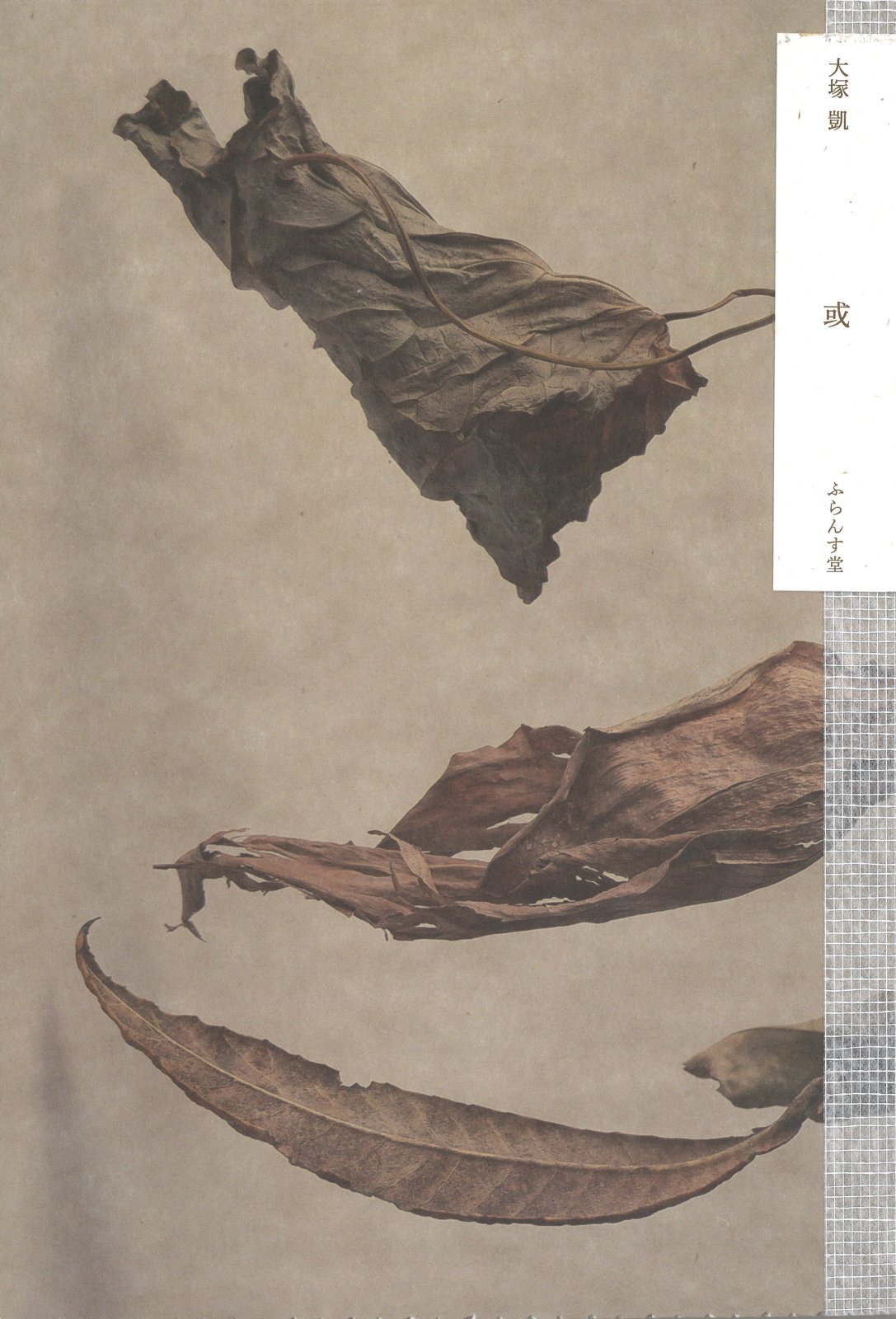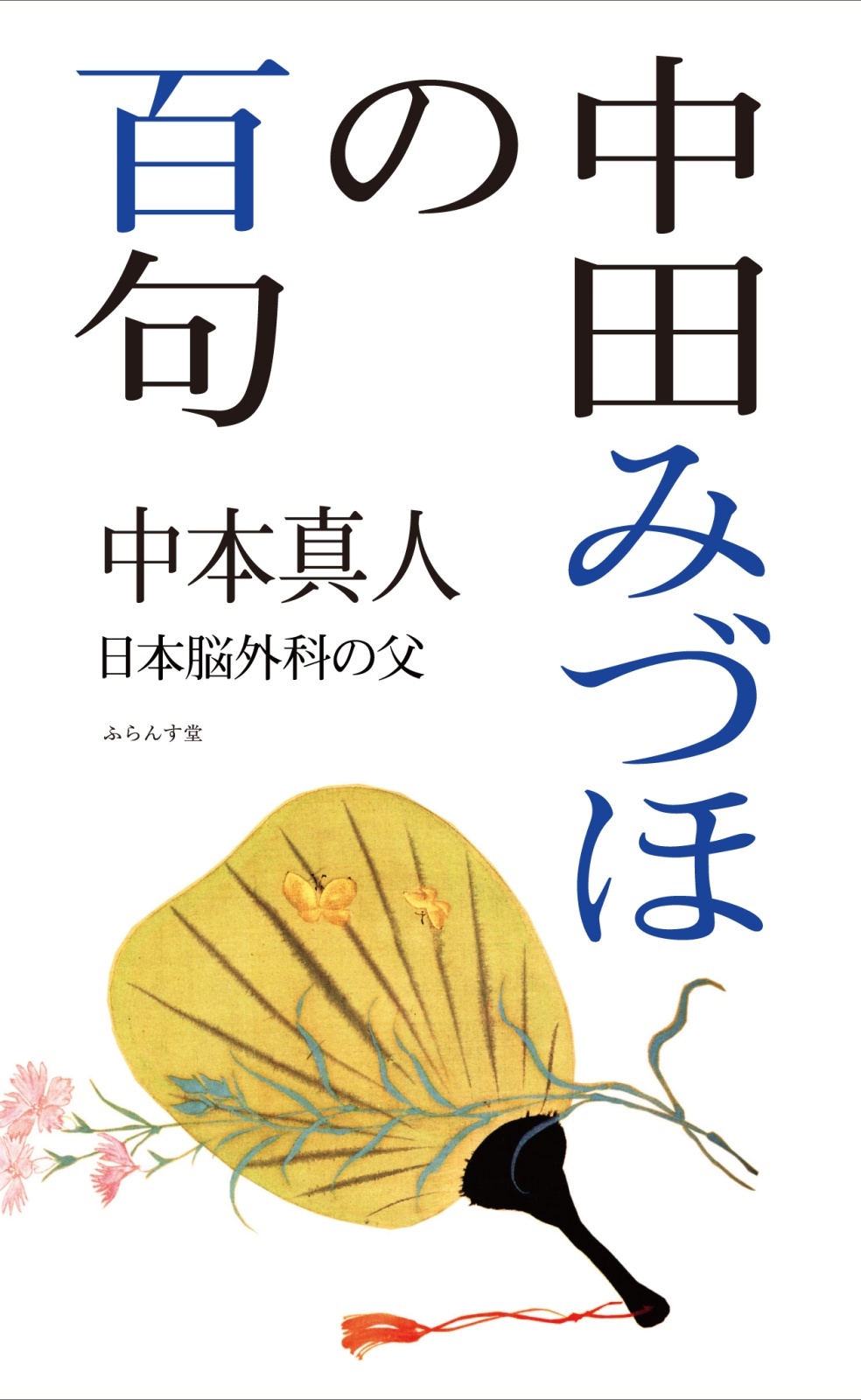岸本尚毅の吟行日記122016.6.30
俳句実践講座
岸本尚毅さんが指導をされている句会を取材しています。
実践の場で俳句をどうつくるか、大変参考になると思います。
●岸本尚毅作
人間は弁当が好き冬の雲
裸木のつぶさに苔の肌へかな
やはらかにコキと鳴る肩冬の雲
冬晴や日ざし明るく雲多く
広からぬ芝枯れてある座敷かな
草青し冬の日ざしにうちそよぎ
師走とはかくも静かや蟻が這ふ
●岸本尚毅特選
世田谷の小春の町に来てをりぬ 章
枝の影額にありて日向ぼこ 紀子
短日の日のあるうちの帰宅かな 定生
鳥小屋の中の巣箱や冬ぬくし 昌子
胸はつて姿勢よき犬冬木立 美緒
灯下なる革のコートに雨の粒 定生
広縁をゆくひとありて枯木宿 喜代子
植替へてある葉牡丹の小さかり 章
学校は古く冬木は育ちけり 定生
日の当る冬の水にも馬臭かな 八江
鴉鳴く冬の三時の日ざしかな 美緒
●尚毅選
外套を脱いで明るき椅子に読む 八江
座布団の薄くて小さき冬座敷 章
常磐木に固き冬芽の立つことも 董子
残る葉を鳴らすことなき冬日和 八江
籬あり銀杏落葉のうち積もり 章
赤き実の生る家並や神迎 紀子
せはしくはあれど事なく年の逝く 董子
閑居して待降節の赤きもの 喜代子
ひとの耳朶うす紅色や落葉径 紀子
高空をあふぐ懐炉の熱さかな 昌子
冬の日に今度は背中向けてをり 章
落し物落葉の中に捜しをり 章
硝子戸の埃まみれや日向ぼこ 八江
枯園に木のごみ箱のうれしかり 昌子
をみなごの裸足になつて園枯るる 昌子
背凭のあるがうれしき日向ぼこ 定生
梅林や掃かれぬ落葉きよらかに 喜代子
お茶室の庭つづきなる落葉山 八江
脱ぎ置きし帽子焚火の匂ひあり 章
籬より街を見下ろし冬籠 紀子
落葉踏む火事のサイレン聞きながら 定生
硝子戸の外は大空冬座敷 美緒
自転車は楽し冬日の胸にあり 章
冬帝は動かぬ雲を従へて 紀子
●岸本尚毅氏の講評

○世田谷の小春の町に来てをりぬ
これは世田谷が効いてますよね。品川、板橋、葛飾でも多分だめですよね、これは世田谷でなくてはという感じがしますね。
○庵にけふ人の声ある冬紅葉
「人声のある」となってましたが、これは「人の声ある」の方がいいでしょう。
わたしがいただかなかった句について言いますと、
○せかるるやポインセチアが街に出て
「街に出て」という言い方はわかるんですけど、この「出て」というのは、富安風生の「街の雨鶯餅がもう出たか」の「出る」なんですが、ウーン、でもわたしだったら、「ポインセチアを売る巷」ぐらいにしたらどうか、と思います。

○この丘へ幾筋も径落葉径
「幾筋」の「筋」の響きがよろしくないんで、「いくつも径(こみち)」とし、下五は「木の葉降る」としたらどうでしょう。
○足元に風立つてゐる十二月
「立つてゐる」というのを直したいですね。二つの違和感があります。まず「立つて」というのは理屈ではないんですが「立ちて」なんですよね。「立つて」と 言うとなんだか人間が立っているような、風の場合は、『風立ちぬ』という小説があるものだからどうも、「風立ち」と言いたくなるんですよね。そして「風が 立つ」というのは瞬間のことなんで、「ゐる」ということとは矛盾するんですね。人間ならじっと立っているいわゆるstandingなんだけど、「風が立 つ」ということは、たぶん風が吹きはじめることではないかと思うんですね。ずっと吹いている状態は「風立つ」ということではないですね。だから、ここは 「風立つことも」としたらどうでしょう。
「足元に風立つことも十二月」。でもこうすると面白くないですねえ。やはり「風立ちてゐる」か。それもヘンなんだな、するとやっぱり「風立つてゐる」か、元の方がいいのかなあ、と結論がでませんね。
○家々に窓ありて澄む冬日かな
「澄む」がなんとかとれないかなあと思いまして、僕だったら「家々に窓ある上の冬日かな」と。
○広からぬ芝枯れてゐる座敷かな
これは僕の句ですが、「枯れてゐる」ではなく、「枯れてある」の方がいいですね。
○片々と急がぬ雲や枯るる中
「片々と急がぬ雲や」まではいいですね。「枯るる中」を「冬ざるる」としてはどうでしょう。「中」がとれるといいですね。
●おことわり
このページは、俳句愛好者の作句の勉強の一助とする目的で、岸本尚毅さんが句友諸氏と個人的に行っている句会の様子を紹介させて頂くものです。この句会は 私的な会であり、部外者には一切オープンにされておりません。そのため日付・場所・作者名は非公開です。お問い合わせはご遠慮ください。引用された作品の 著作権は、実在する各作品の作者に帰属しますのでご注意ください。