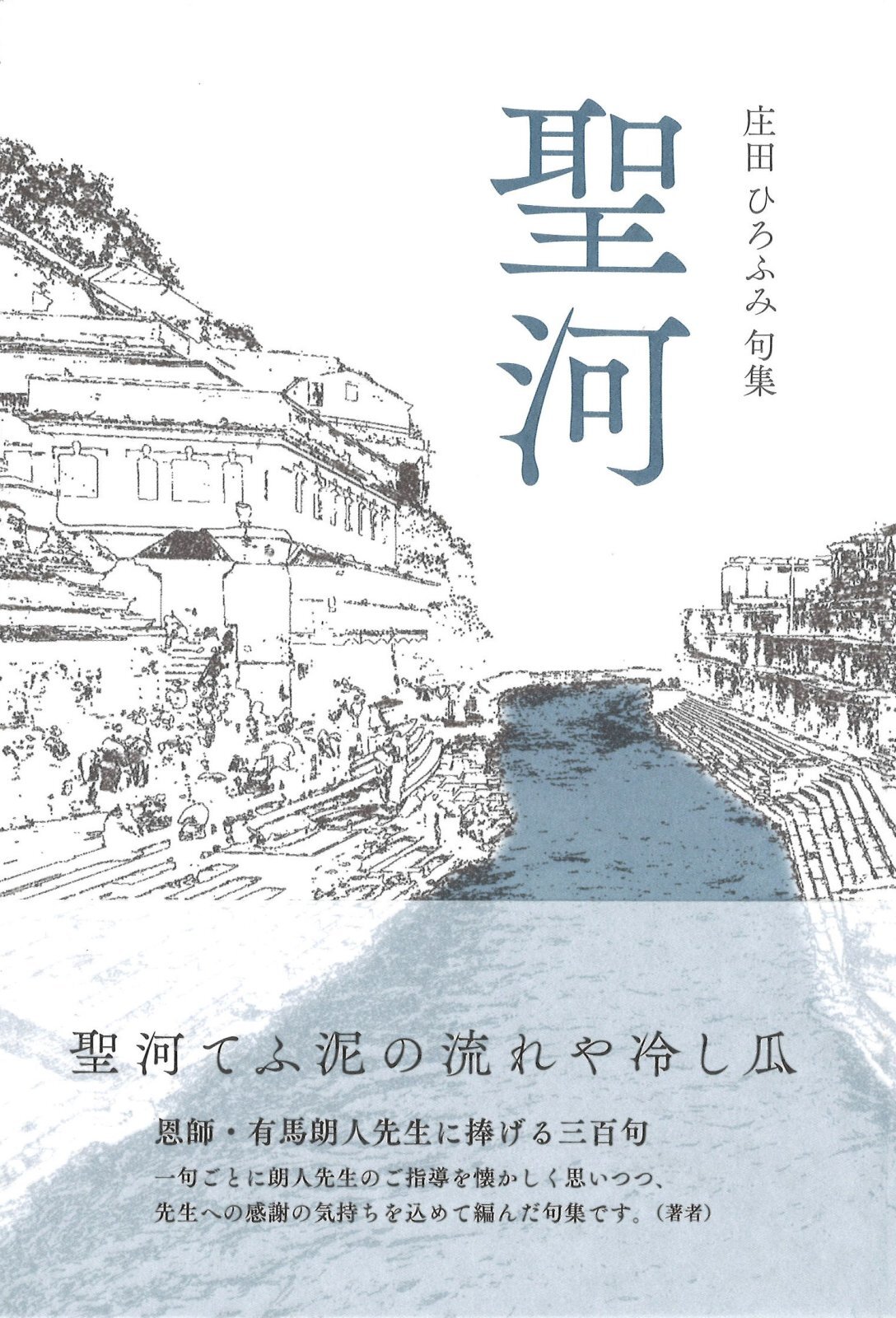手の汚れ 加藤かな文2010.5.23
春愁の夕べを帰る手の汚れ
(『月光抄』)
第一句集『月光抄』(昭和24年)所収。昭和14年、信子二十四歳の作品。この年の十一月に結婚した彼女は、二年後に夫と死別。九十歳で亡くなるまでの長い寡婦生活を送ることになる。
わかりやすい信子とわかりにくい信子がいる。「乳首より出づるものなし萩枯るる」(『月光抄』)、「欲情やとぎれとぎれに春の蝉」「ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき」「ひとり臥てちちろと闇をおなじうす」「きさらぎの風吹ききみはひとの夫」「女体の香われにもありや梅雨晴れ間」「梅雨の月いま泉わく森もあらむ」(『女身』)。こうしたわかりやすい信子は、「道順はここを真直ぐ夏の暮」「朝に夕に落葉掃く日のなほありや」(『草影』)における晩年の信子でもある。
ところが、掲出句の〈手の汚れ〉はわかりにくい。この信子の〈手〉は、未亡人のうら若い肉体とも年老いた肉体とも無縁。また、それが〈春愁〉の具象化にしては重すぎと感じるのは、〈手の汚れ〉が「手を汚す」(罪を犯す)という言葉を連想させるからだろう。どうやら、あらかじめ信子は何かを背負っている。人生に翻弄される以前から。出自のわからぬ何かは、その後もしきりに信子のもとを訪れる。「今なら殺せる冬の蜂畳匍ふ」(『晩春』)、「罠もろとも獣がうごく霧の底」「共に焚かれ枯菊と縄似てしまう」「三月の終りの紙を切りきざむ」「明日は死ぬ寒鮒の水入れ替える」(『新緑』)、「瓶ふって虫をころがす夏休み」(『緑夜』)、「日の浜にくらげは水となりゆける」(『花影』)。信子の心のざらつきを、仮に原罪意識とでも呼んだとして、いったい何がわかったことになるだろう。俳句を書き記すその〈手〉に罪業が宿るなどと、誰が思ったりするものか。
[著者略歴]
加藤かな文 Kanabun KATOU
1961年9月6日、愛知県生まれ。1984年より愛知県立高校勤務。1993年、「槐」入会。岡井省二・児玉輝代に師事。1997年、第6回槐賞受賞。2001年、「槐」退会、「家」創刊同人。2009年、第一句集『家』上梓。2010年、同句集により第33回俳人協会新人賞受賞。現在、「家」編集発行人、俳人協会会員、日本文藝家協会会員。