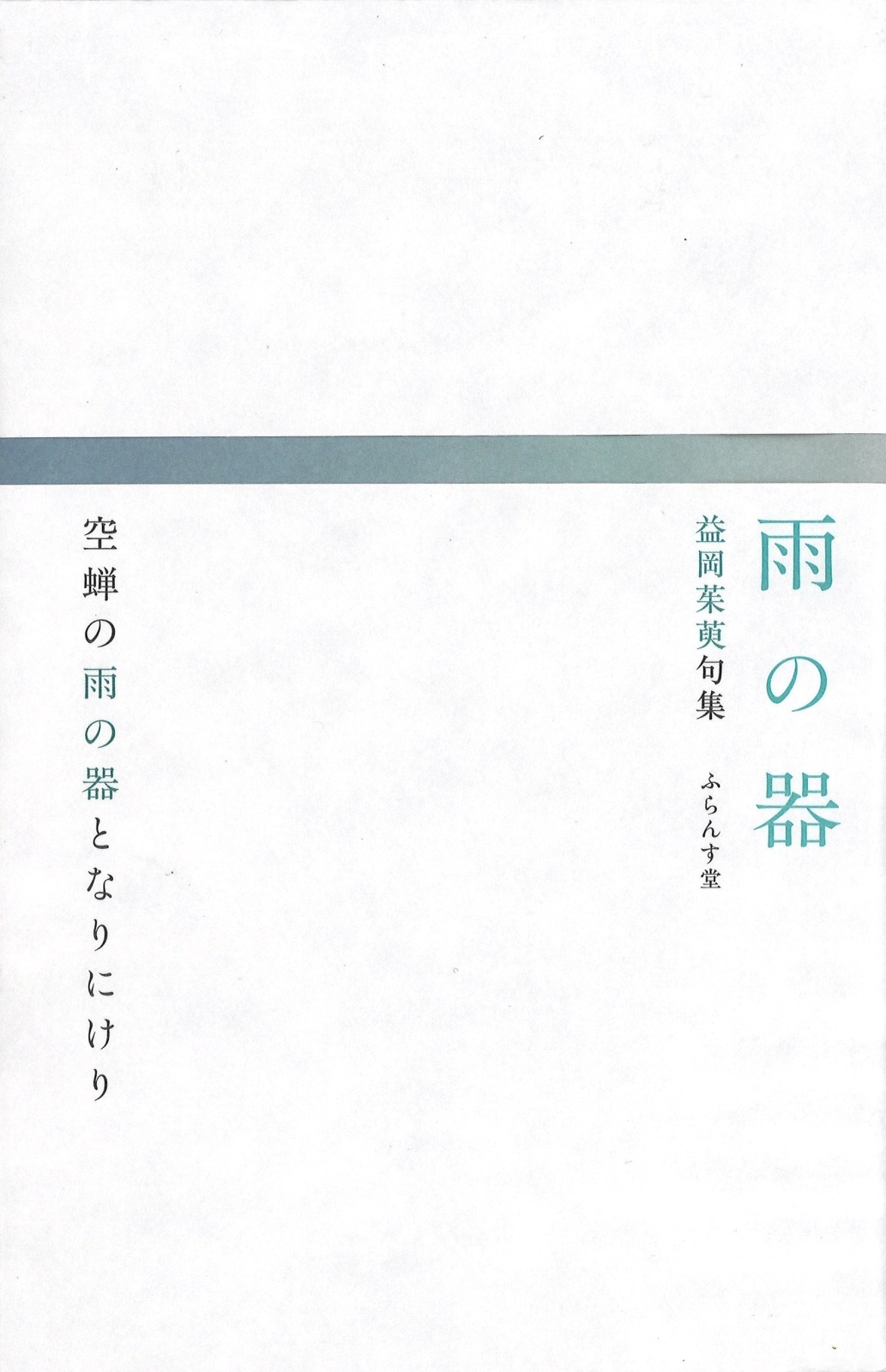掟の崖 関 悦史2010.6.6
蝸牛まひるの崖をころげ落つ
(『緑夜』)
崖を転げ落ちていったところで、ものがカタツムリでは音らしい音も立てまい。今まで崖の上にいたということの方が嘘であったかのように、何の変化も見せぬ、人でいえば眉一筋動かさない崖上の景だけが残る。ロバート・ブラウニングの「蝸牛枝に這ひ、/神、そらに知ろしめす。/なべて世は事も無し」をもじれば、「蝸牛崖を落ち、/虚無、真昼に知ろしめす。/なべて世は事も無し」といったところだ。
古池に飛び込んだ芭蕉の蛙は姿を消す代わりに古池と複合し、己を呑んで静まりかえる古池に妖しい生気を帯びさせ、永遠の沈黙に近い何ものかを現成(あるいは「演出」であろうか)させるに至ったが、蝸牛はただいずこかへ姿を消すのみ。
ではこの句は、単に一体の生きものの消失を冷然と突き放す「まひるの崖」の虚無だけを描いたものであろうか。
そう割り切るには落ちていった蝸牛というものの渦巻く形状それ自体が、少々人くさい蛙などと違って、ひとつの混沌を孕んでいはしまいか。
造化の神秘などといえば大仰に過ぎるが、大は銀河系から小は遺伝子に至るまでを貫く渦・螺旋の幾何学的パターンを殻に負い、一方、中からはみ出す濡れた軟体には、生命というもの自体を形にしたらこうもなろうかという生々しさをまつわりつかせた、雌雄同体の一生命。「まひるの崖」の世界の縁の如き切迫が、この蝸牛一体の微小の怪しみを際立たせ、そしてあっさりと消し去る。悪意というのとも違う巨大な笑いが、背後に微かに響く。この「まひるの崖」はこの蝸牛を落とすためだけに在り続けていたのかもしれない。あるいは「まひるの崖」と「蝸牛」とは、あまりにも全面的に明白で、謎がないこと自体が謎である、一対の機械のようなものであろうか。
[著者略歴]
関 悦史 Etsushi SEKI
昭和44年、茨城県生まれ。
平成14年第1回芝不器男俳句新人賞城戸朱理奨励賞。
平成21年第11回俳句界評論賞。同年「豈」同人。