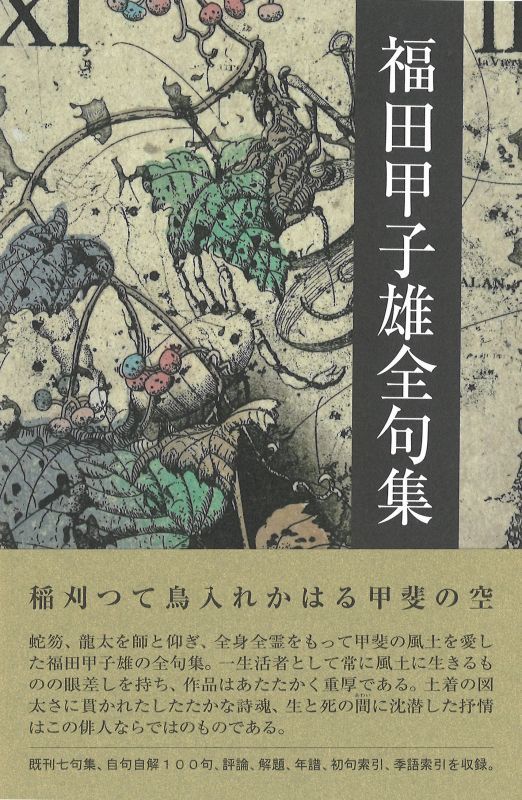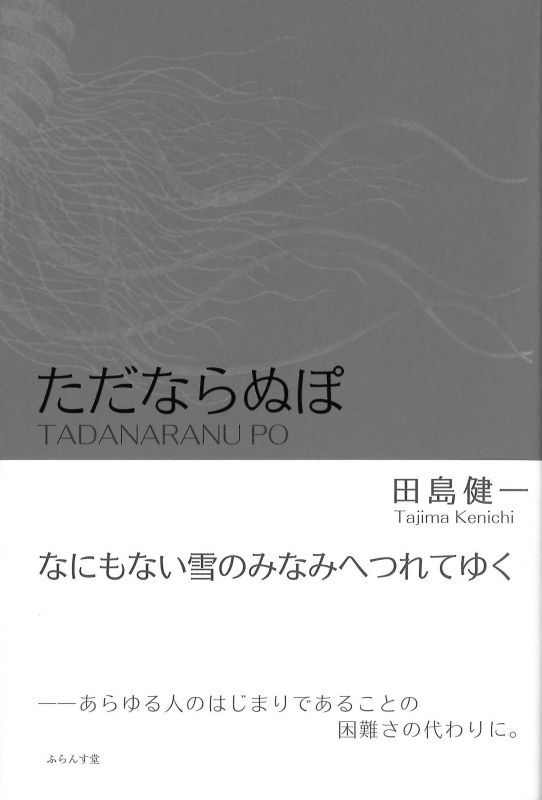赤い揺曳 田中亜美2010.8.8
煖炉ぬくし何を言ひだすかもしれぬ
(『女身』)
かつて桂信子の俳句について、フランス文学者の生島遼一は次のように指摘した。「フランス古典文学のえらい作家はみな元来内にあらあらしい激情をもつてゐた人で、それを抑へるために端整な規矩や文体を必要としたのだといふ。(中略)行儀のいい、冷静なしとやかな信子さんもやはり内にあらあらしい激情をつつんで、それをあゝいふ端整そのもののやうな表現でおさへてゐる古典主義者なのであらうかどうか」。(『月光抄』。傍点部筆者)
新興俳句の作家と目されることの多い桂信子という俳人が「古典主義者」かどうか。日本文学や俳句史における一般的な「古典」の定義にそっくり当てはまるかということについては、疑問符がつくだろう。しかし、「あらあらしい激情」ゆえに、「端整そのもののやうな表現でおさへてゐる」のが古典主義であるのだという、生島の西洋文学的な理解に鑑みたとき、桂信子とは、静かな佇まいのなかに、絶えず激しい情熱を秘めているという点で、永遠に「古典主義者」の王道をゆく女性俳人なのだと、ふかく納得させられる。
掲句は第二句集『女身』所収。煖炉の前でぱちぱちと爆ぜ、ゆらゆらと燃える炎を見つめている。「何を」とは、いったい何なのか。句またがりの措辞による切迫した音律と相俟って、裡がわより迸り出る何か、デモーニッシュな激情が、うねるように伝わる。煖炉に赤く揺曳する炎の熱と感触が、読み手であるこちら側にも、乗り移ってくるかのようだ。
『女身』には、「寡婦われに起ちても臥ても鶏頭燃ゆ」「子への愛知らず金魚に麩をうかす」などの境涯詠の一方で、「ひたすらに赤し颱風前の薔薇」「朝の玻璃つめたし遠の曼珠沙華」といった清新な写生句も少なくない。いずれも赤の色彩感が目を惹く。信子の「アラフォー」時代の句集だが、哀しみや諦め、さびしさだけでなく、人生の<朱夏>ともいうべき旺盛な時間を生き抜いてゆく、ひとりの女性の姿が見えてくるようで、胸を打つ。
[著者略歴]
田中亜美 Ami TANAKA
昭和45年東京生まれ。
平成10年「海程」入会。金子兜太に師事。
平成18年 第24回現代俳句新人賞
著作に『現代の俳人101』(共著・新書館)、アンソロジー『新撰21』(邑書林)。
現代俳句協会・国際俳句交流協会会員。