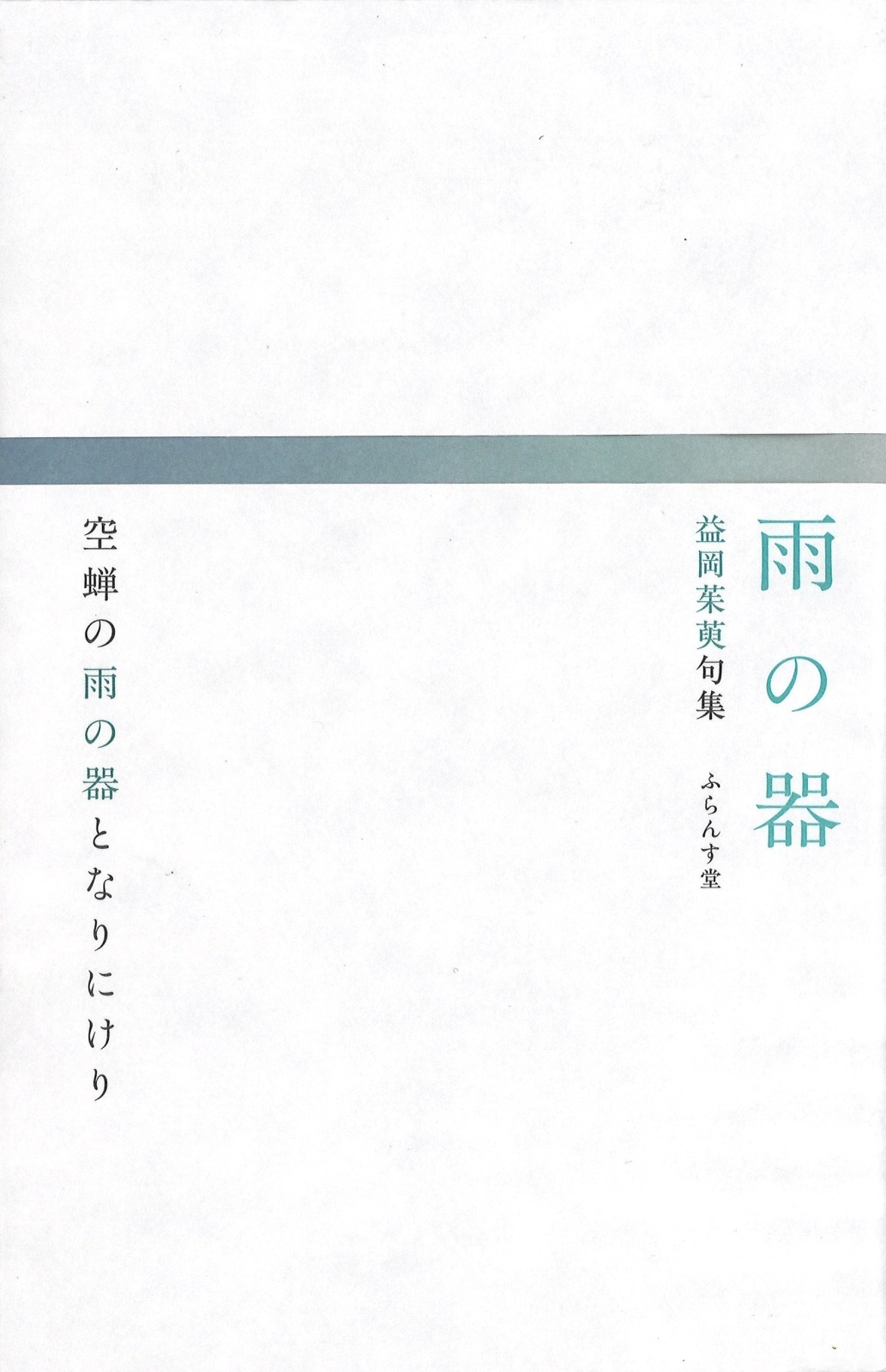長谷川櫂さんを訪ねる2009.11.1

2009年の11月1日の日曜日に俳人の長谷川櫂さんの仕事場に若い俳人の方たちとご一緒におじゃまをした。
太平洋を目のまえにしたその仕事場はあかるい日差しがそそぎこみ、晩秋の海はやさしく静かだった。
伺ったのは、高柳克弘さん、鴇田智哉さん、日下野由季さん、神野紗希さん、関悦史さん、宇井十間さん、山口優夢さんの7人の俳人の方たち。 俳句についておおいに語りあう一日となった。
この日の交流の痕跡をとどめておきたく、皆さまに原稿をいただきました。
「長谷川櫂の俳句の一句鑑賞」とそれぞれの作品一句です。
秋晴を来て星空を帰りけり 櫂
海といふ日溜まりに冬来たりけり 山口優夢
江の島の灯の窓越しに秋惜しむ 日下野由季
海の辺にテーブルのある秋の昼 鴇田智哉
うねりては穢を呑む海よ寒日和 高柳克弘
世界側は鴎の白の秋の海 関 悦史
オリーブの枝の細さよカーディガン 神野紗希
天気雨いくたび人類後の地球 宇井十間
長谷川作品一句鑑賞 ||
宇井十間 | 神野紗希 | 関 悦史 | 高柳克弘 | 鴇田智哉 | 日下野由季 | 山口優夢 |
●長谷川作品一句鑑賞
老人のすぐに舌打ち秋暑し
地を打ちて音なかりけり蝶の秋
団子食ふ常磐木落葉秋の日を
●宇井十間
白露やこぼれこぼれてとどまらず
第7句集『初雁』から、2002年の作とある。大きくみずみずしい葉の上 に、透明な露の玉がのっている情景を想像してみよう。露はときどき地に落ちてきえてしまうが、あとからあとから露がながれてきて同じ玉をつくるのである。 まるでディズニーアニメの一シーンのように美しいクローズアップである。「こぼれこぼれて」という中句は平明だが、なかなか出てこない表現であろう。
子規の短歌に「松の葉の葉毎に結ぶ白露の置きてはこぼれこぼれては置く」がある。 掲出句の表現はこれと比べると、余計な叙述を切り払って簡潔になっている分だけ、白露の美しさが際だつ。
長谷川俳句には、このようにきわめて叙情的できめの細かい表現がある一方で、非常に句柄の大きい豪胆な句もときどきある。掲出句はむろん前者の例である が、「鷹飛んでとらへし花のごときもの」(『松島』)「大いなる虚空にすくふ鷲であれ」(『初雁』2002年作)などは後者の好例である。
●神野紗希
わだつみの眠りの中をゆく鯨
海の神であるわだつみが眠りについている間、海中世界は、どこまでも静かだ。音もなく、変化もない。そん な空気のような海の中を、まっすぐに進んでゆく鯨。差し込む太陽の光の柱を、ときにくぐり、ときにさえぎりながら、カメラの視界の中で大きくなり、そして 消えてゆく。鰭を動かすでもなく、大きく口を開けるでもない。止まっているようでありながら、その実、確かに進んでいる。キューブリックの映画「2001 年宇宙の旅」で、宇宙空間の暗闇を、宇宙船が淡々と進んでゆくシーンにも似ていると思うのは、鯨が、生き物というよりも、一つの物体のようだからだろう か。
ここで鯨は、ポセイドンのような人間の形をした神が統べる、海という大景の中を掠めてゆくのではない。わだつみという巨大な神の胎内を、孫悟空がお釈迦様 の掌の上で飛び回っているように、はみ出すことなく、静かに横切っていく。海のゆたかさ、鯨の生命の静謐さ、冬の光のかそけさ。私たちが、決して目にする ことのできない、しかし、世界に必ず存在する景色の描写が、夢にも似て、強く印象付けられる句だ。この句をつぶやくたび、運命といった語が、なぜかリアル に感じられるのである。
●関 悦史
春の水とは濡れてゐるみづのこと
水が濡れると言った途端「濡れていない水」が析出され、「春の水」の特異性がそこから切り出されることにな る。日常的事物たる「水」に季語という別な言語制度の時空から「春の水」が不意に介入し一体化するという事態が起き、それがほとんど性的な愉楽感を生じさ せる。いわば俳句という制度自体を組み込んだメタ俳句的な成り立ち方をしているわけだ。この句は、西脇順三郎の詩「雨」をプレテクストとして持つ。女神と しての雨があらゆるものを濡らし、神化・賦活してゆく動的な輝かしい詩だが掲句はそこから雑神性を切り捨て静謐なたゆたいの世界へ移調した。日常的時空と 季語的時空の差に拠っているだけでなく、先行作を持つ点でも間テクスト性の際立つ例外的な句だが、却ってそこに作者の資質が蒸留された形で鮮明に現われて いる。宙に浮いた透明な球ででもあるかのようなこの句の姿の単純さ、澄明さ。
●高柳克弘
一本の冬木に待たれゐると思へ
長谷川氏がとある座談会で、飯田龍太氏に「射程を長く取りなさい」という言葉をかけられ、以後そのことが常に 胸中にある、ということを語っていた。この言葉は、掲句とともに、私の心中にも深く刻まれることとなった。はるか彼方に立つ「冬木」は、目指すべき詩境の 隠喩として屹立している。夏の緑の木は木陰を作り、いかにも人を待っているようであるが、「冬木」は御世辞にもそのようには見えないはず。それでも「待た れゐると思へ」と自分に言い聞かせているところに、詩人として生きていく孤独が凝縮されている。
●鴇田智哉
数本の木賊のもとの昼寝かな
木賊の形はおもしろい。まっすぐなようで、よく見ると、ゆるゆると曲がっている。横になった体に対して、木賊は縦にむかってゆるゆるとのびている。それがいくつかの夢を誘うのである。というか、木賊そのものが、夢の形だと言ってもいい。
「木賊」という能があるそうだ。能の舞は、過去と今が結びついた夢だから、そうした雰囲気も、この句の背景にはあるように思う。
●日下野由季
春の月大輪にして一重なる
第一句集『古志』所収。二十代の頃の作品であるが二十代にしてすでにこの美意識の高さはどうであろう。春の月そのものを詠んで、これほどまでに美しい句を私は他に見たことがない。思わず溜め息が出るほどだ。
「大輪」も「一重」もともに花の形容に使われる言葉であるが、春満月の堂々たる姿を「大輪にして一重なる」と花に見立てたその大胆で大掴みな把握が、実 景を超えて、対象の持つ本質的な美をより際立たせているのだ。大胆かつ繊細な表現はまた、琳派の絵を彷彿とさせるものがある。
氏の大胆さはどこから来るのだろう。ふとそんなことが気になり始めた。初期の作品であるこの句に限っていえば、若さ特有の自信や気概がこうした潔い把握 を生み出したと見ることもできる。けれどもこの大胆で大掴みな把握が現在の作品へと繋がっている氏の特徴の一つであると思うと、それはもっと根本的なもの だ。もしかしたらそれは生き方の潔さと通じているのかもしれない。
●山口優夢
うつすらとまぶたのありし蛇の衣
蛇の衣を見たことが一回だけある。研究室で隣に座っている女性がその日の朝拾ってきたという蛇の衣をびろーん と見せてくれたのだった。ごわごわというかびろびろというか、ビニールのような、魚の皮のような、そんな感触。はたしてその頭の部分にまぶたがあったかど うか。ただ、この句では「し」という過去の助動詞「き」の連体形を使っているところからすると、もうそのまぶたはとれてしまったのかもしれない。失われや すい、うすいまぶた。そんな細かなフォルムを描写することで、衣を脱ぎ捨てていった蛇の存在感をありありと感じさせるところに大変興味を覚えた。