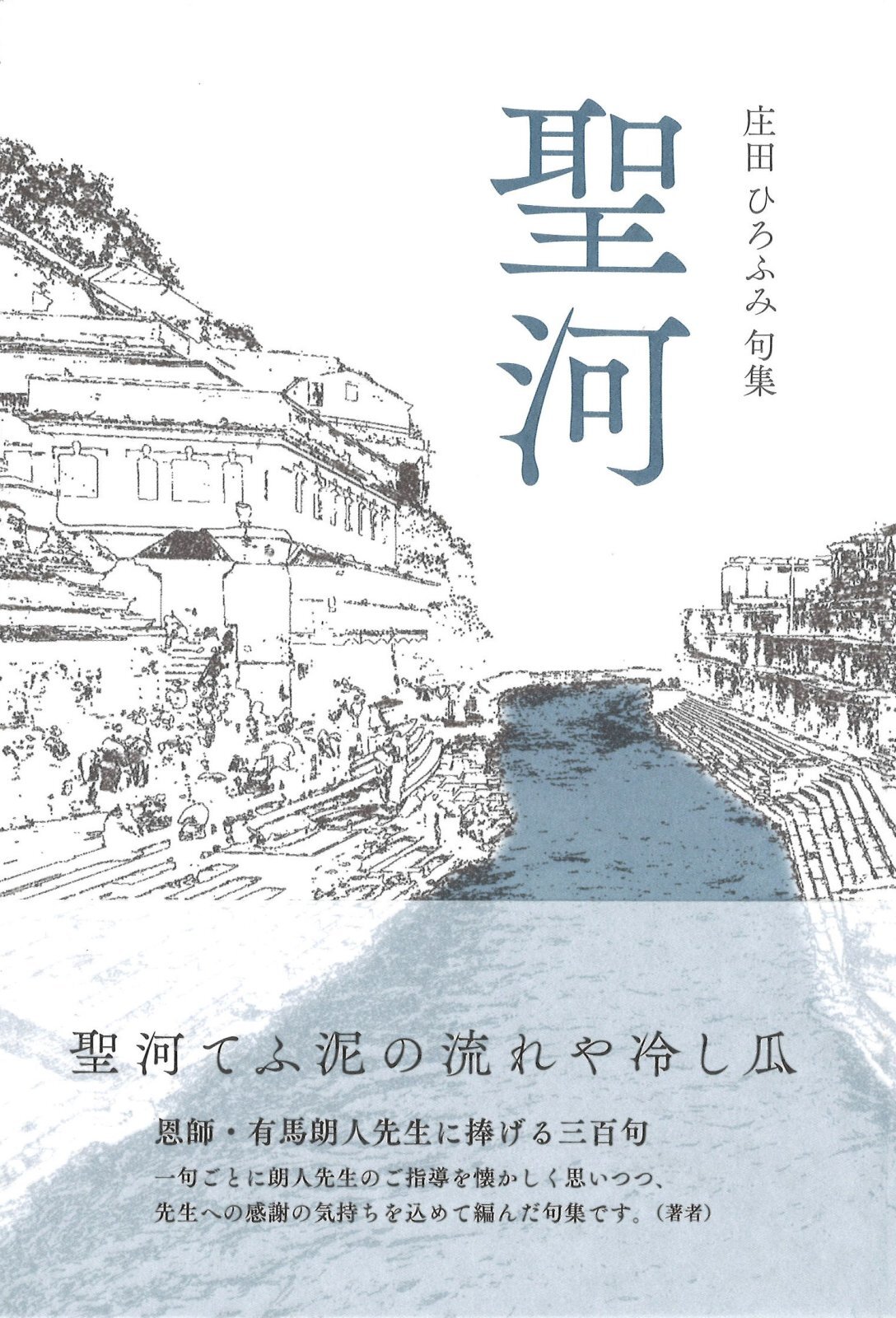田中裕明「夜の形式」とは何か2010.3.8
はじめに

俳人の四ッ谷龍さんより、「田中裕明のことをテーマにした講演会を小さな規模でもいいからやりたい」と相談をいただいたのが、昨年の秋だったでしょうか。四ッ谷さんの当初のご意向では、「田中裕明賞等とからめて開催できるだろうか。それがむずかしいようであれば、現代俳句協会青年部に頼むことも考えている」ということでした。「2010年は第一回田中裕明賞が決定する年にあたり、そう言う意味からいってもふたたびここで田中裕明を顕彰するにもよい機会であると思えました。また、四ッ谷龍さんは、「田中裕明賞」の選考委員のおひとりでもあります。その四ッ谷龍さんの田中裕明理解を知ってもらう上でも意味ある講演会であるように思えたのでした。ただ、田中裕明賞にからめて何かイヴェントをするという計画は予定しておらず、また、ふらんす堂はこれまで講演会なるものを開催した経験もなく、四ッ谷さんのお気持ちに応えるにははなはだ心もとないものがありました。そこで現代俳句協会青年部に頼んでもという四ツ谷さんの当初のご意向をふまえて、現代俳句協会青年部との共催というかたちでの講演会としたらどうかと四ッ谷さんにご提案し、それを青年部部長の橋本直さんにご相談したのです。この提案を青年部はこころよく受け入れてくださり、橋本直さんを中心に青年部のお力をかりながら2010年1月24日の講演会にこぎつけたのでした。当初は四ッ谷龍さんおひとりの講演ということでしたが、橋本直さんの提案によって田中裕明研究誌「静かな場所」のメンバーの方たちに「田中裕明について語ってもらったらどうだろうか」という提案がなされ、こちらのお願いに快諾をいただいた森賀まりさん、山口昭男さん、対中いずみさん、満田春日さんの4人の方がパネラーとして出席くださったのでした。講演会のよびかけに予想外の多くの申し込みがあり途中会場の変更があったりしてご迷惑をおかけしたりしたのですが、なんとか1月24日の講演会を迎えたのでした。場所は東京・池袋にある豊島勤労福祉会館。三部形式にわかれ、第一部は四ッ谷龍氏公講演「田中裕明『夜の形式』とは何か」、第二部は、「田中裕明の人と作品」と題して、森賀まり、対中いずみ、満田春日、山口昭男の各氏にそれぞれの思いを語っていただき、第三部は参加者による「懇親会」となりました。100名を超す方々の参加をいただき、会場は田中裕明への理解を深めようとする参加者の方々の思いが満ちているようにおもえました。また、この講演会のために結社をこえて若い俳人の方たちがご尽力をくださったことも嬉しいことです。
第一部は四ッ谷龍さんにより、コンピュータの最新技術を駆使して絵画や音楽を紹介しながら「夜の形式」とは何か、への深い考察がなされ2時間という時間があっという間でした。第二部は、パネラーの方4人に四ッ谷龍さんが加わって、橋本直さんの司会でそれぞれが「田中裕明の人と思い出」を語るというもの。おひとりおひとりが語る田中裕明像は、いまもなお四ッ谷さんをはじめパネラーの人々の心にふかく内在する田中裕明が丁寧に語られ会場に集まった人たちにとって、「友人としての田中裕明」「師としての田中裕明」「夫としての田中裕明」を通して俳人田中裕明の姿が彷彿としてきた時間だったのではないかと思います。
そこでふらんす堂のホームページ上に「夜の形式」というサイトを立ち上げこの度の講演会について感想をいただくことに致しました。
この講演会に関わった方々とご参加くださった方の何人かの方たちにお原稿をお願いいたしました。
また、ほかのサイトにて掲載されたものも許可をいただいてここで紹介させていただきます。
このサイトは生きていて、これからも書かれていくであろう田中裕明についてはできるだけリンクをはっていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いもうしあげます。
田中裕明の作品が多くの人に読み継がれていってほしい。
作品をとおして田中裕明は生き続けていくのです。
講演会に関わった皆さまにこころより感謝申し上げます。
2010年3月8日 ふらんす堂 山岡喜美子
講演を終えて

(c)FURANSUDO
四ッ谷龍:講演を終えて
今回の企画で、聴衆の皆さんに田中裕明の俳句を新しい面から理解していただけたなら喜ばしい限りです。さらに彼の散文のユニークさにも気づけてもらえたのではないでしょうか。
「夜の形式」という文章を手がかりにして、講演内容を準備していきました。自分の考えていることが裕明の考えにほんとうに合っているのかどうか、直前まで悩んでいました。第二部のパネル・ディスカッションで森賀まりさんから、こちらの発想が大筋で外れていなかったことを裏付けていただき、よかったと思いました。昭和54年のエゴン・シーレ展の話が出ましたが、私は学生時代に西武美術館で観て強く印象を受け、そのときの図録は今でも家にあります。同じ巡回展を裕明さんとまりさんがご覧になっていたと知って、心を打たれました。
当日佐世保からお越しいただいた荻野雅彦さんとは初対面でしたが、講演内容について有意義なご見解をいろいろうかがえました。たとえば「夜の形式」の最後の一文
「ほんとうにずいぶん前にも考えていたことなのだが、いま手にしているのは夜の形式ではないようだ」
この部分を、私は「今、自分が作っている俳句は必ずしも夜の形式とは言えないようだ」という意味にとりましたが、荻野さんは「今日の俳句界を占めているのは夜の形式の俳句ではないようだ」というように解釈しておられました。「週刊俳句」サイト上のレポートで、上田信治さんもこの部分を現代俳句への批判とする解釈を示しており、なるほど、そういう見かたもできるなと思いました。このように、今回の講演を批評的に受け止めてさまざまに展開していただけるのは、たいへんありがたいことだと思います。
講演が終わったとき、高橋睦郎さんが話しかけてくださり、「詩の世界で『夜』がもつ重要性に最初に気がついたのは、リルケだと思うよ」とご教示くださいました。実は 下調べをする中で、リルケを押さえておくべきではないかと着眼してはいたのですが、きちんと消化して語る自信がなかったので、あえて触れませんでした。
「夜」や「夜の形式」について語るべきことはまだまだありそうな気がしますが、その解明は皆さんの力にも期待したいと思います。
四ッ谷龍 Ryu YOTSUYA
昭和33年札幌生まれ、東京育ち。昭和49年「鷹」に入会。
昭和62年、冬野虹とともに二人誌[むしめがね」創刊。
平成9年、ホームページ「インターネットむしめがね」開設。
著書に句集『慈愛』『セレクション俳人・四ッ谷龍集』『大いなる項目』(近刊)
橋本 直:勉強会を終えて
昨年、三軒茶屋でおこなった青年部勉強会の懇親会のおり、参加してくださっていた四ッ谷龍さんがふいにあらたまって、青年部の勉強会で田中裕明について話したい、ついては田中裕明に縁の深いふらんす堂さんと共催の形でできないだろうか、と今回の企画について打ち明けられた。私たちとしては一も二もなく賛成したが、当初いつもの勉強会に近いイメージではじまったこの企画は、第二部で裕明令夫人である森賀まりさんをはじめ「ゆう」の系譜をひく俳人の対中いずみさん、満田春日さん、山口昭男さんをお迎えする事も決まり、協会に関係なく若手俳人の助力を得、会場変更の必要がでるほどの参加者がきた。
これは新鮮な驚きで、平易なようでいて謎めいたの句の作者である田中裕明とその作品への興味と、裕明の親友であり優れた俳人でもある四ッ谷龍さんが久しぶりに表舞台に立って、亡き友の残した謎について語るという事への期待の表れだったのだろう。会としては大成功だったし、ここから先の展開をとても楽しみにしている。皆様に感謝。
以下舌足らずな言い方になるが、俳句形式の面白さの一つは、最も日本語の問題に近い文学テクストであるということで、いかに読めるかということといかに詠まれたかということが共時的に語れてしまうことにある気がする。俳句で一昔前の散文の作家論作品論のように素朴に言うことはたぶんナンセンスだし、テクスト論を適用しても本来の理論の目的である仮想敵があまりにも弱すぎて面白くない。散文なら読書行為論として成立するような議論も作者と読者の両方の行為論の場へ引っ張り出されていくようなところがあり、こうと規定したり、すべて一対一対応するような、二進法的なシステムの組み上げようがないたたずまいをしている。ゆえに、先に「俳句形式」などと使っていながらも、同時にそれは形式ではないのだ、と、今はそのようにいうしか手の内に言葉がみつからない。
橋本 直 Sunao HASHIMOTO
1967年愛媛県八幡浜市生まれ。「豈」「鬼」所属。神奈川大学講師(俳文学)。2009年より現代俳句協会青年部部長。然別の森の中の道で一人、真闇を経験したことがある。目が目の前の手さえ知覚しない感覚は、夜目を瞑ることとは明らかに違っていた。
森賀まり:記念
素晴らしいシンポジウムのあと、同じ「夜」を冠した田中裕明の最後の句集『夜の客人』を開きました。この句集の題について、山岡喜美子さんとのメールのやりとりが残っています。「夜の」という限定が作品の世界を狭くするのではないか、また田中の持つ向日性に合わないのではないかという山岡さんの言葉に田中は次のように返しています。
昔、角川賞の受賞の言葉に「夜の形式」という短文を書いたのですが、今度の句集のタイトルを「夜の客人」にしようかと、まりに言ったときに、昔「夜の形式」という文があったねと言ってたので(最近の僕の文章は読みもしないのに)なんとなくその記念に、とも思っています。
「夜の形式」はずっと田中裕明の頭にあったのでしょう。
四ツ谷龍さん、主催者の方々、お手伝いいただいたお若いかたがた、そしてお集まりいただいた皆さまに心から感謝申し上げます。よい時間でした。
森賀まり Mari MORIGA
昭和35年6月6日愛媛県生まれ。高校時代より詩を書き始める。
昭和58年「青」入会。
平成3年「青」終刊。平成六年「百鳥」入会。
平成18年「静かな場所」創刊。
句集に『ねむる手』『瞬く』。詩集に『河へ』。ほかに田中裕明との共著『癒しの一句』。
対中いずみ:手応え
『田中裕明全句集』を刊行したメンバーの願いは、「裕明作品を100年後の若者に届けたい」というものでした。今回は、その予兆のような手応えを感じることができて嬉しく思いました。
四ッ谷さんの講演対象となった「夜の形式」は、田中裕明22歳当時のもので、若い頃、田中裕明は哲学的とも言える詩論をよく書きました。私が出会った頃の田中裕明(40歳~45歳)は絶えてそういう物言いはしなくなっていました。易しい言葉で大切なことだけを静かに語る人になっていました。一般論・抽象論は退けて、具体的作品を鑑賞しながら詩について語っていました。俳句が『花間一壺』『櫻姫譚』時代から『先生への手紙』『夜の客人』へと、より洗練され成熟していったように、文章も沈潜していったようです。そういう意味でも、最後の越智氏の質問が時間切れになったのは惜しかったです。もう少し掘り下げてみたいテーマでした。果たして田中裕明の表現は分かりやすい方法に「流れた」のでしょうか。私にはそこに田中裕明のはっきりとした意志があったと思えるし、より俳句に対して本気になったのだと感じられてなりません。いずれにせよ「夜の形式」などの思索もたっぷりと水面下に潜めて、田中裕明という人は氷山の一角としてそこに居たし、氷山の一角のその最高峰として句集『夜の客人』が遺されたのだと思います。
(因みに若い頃の田中裕明の文章に興味がおありの方は、同人誌「静かな場所」3号(『花間一壺』時代)、4号(『櫻姫譚』時代)に全文掲載していますので、どうぞお申し付け下さい。10冊ほど在庫があります。『先生から手紙』時代特集の5号は、現在編集中です)。
最後に、このような機会を作って下さった関係者の皆様に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
対中いずみ Izumi TAINAKA
1956年1月1日生。大津市在住。2000年「ゆう」入会、2004年第4回「ゆう」俳句賞受賞、2005年「ゆう」終刊。同年、第20回俳句研究賞受賞、句集「冬菫」上梓。現在「椋」「晨」「静かな場所」同人。
満田春日:シンポジウムの感想
四ッ谷さんの素晴らしい講演の余韻が消えないうちに始まったシンポジウム。参加者の真剣な眼差しや熱気にすっかり圧倒されました。「静かな場所」の仲間の話も、「ゆう」の編集人は田中裕明とのアイコンタクトで決まった(!)など、初めて聞くことがあり、聴衆側でじっくり耳を傾けたいぐらいでした。
田中裕明の句をテキストとして読めば、「切れ」の俳句だ、という質問者、宇井氏の言葉に、ほとんど田中裕明の人となりや小さなエピソードに終始した私は首をすくめつつ、ふいに50年、100年後に連れて行かれるような心持がしました。生きて息をしていた田中裕明を知る人が一人もいなくなる日、純粋に文字データとしてしか、裕明俳句を読めない日は確実に来る。早世は、それまでの猶予時間を普通よりやや長くとらせることにはなったけれど、ありのままの田中裕明の姿を語り、書き遺すことは未来の俳句のためにも、まだ見ぬ田中裕明ファンのためにも無駄ではないかもしれません。俳句は生身の人間が書くものですから。
「田中裕明は自分のために俳句を作るのではないと明言した。では何のために、という質問に『まりです』と答えた」というエピソードを紹介したとき、ちょっと会場が湧きましたが、冗談めかしながら真実を言ったという気がしてなりません。最も身近で大切なものが、最も遠く崇高なものと一致する、そんなことが田中裕明の生き方にも、俳句にも貫かれていたのでないか。まりさんの第二句集『瞬く』のあとがきにある「遠い空にあるものがふいに身ほとりで輝く」という言葉も、そこに一脈通じるものがあります。
人にはそれぞれの役目があるのでしょう。私が企画させてもらった、6年前の今頃の吟行句会で、田中裕明が代表句の一つとなりつつある「教会のつめたき椅子を拭く仕事」を残したたけでも、私が「ゆう」に行った意味がある、さらに言えば、私が俳句を始めた意味はその一句に繋がっていてもいいと思います。いたずらっぽい笑顔で、おそらくはちょっとはにかんで仰ったであろう「まりです」の一言を思うとき、まだしばらくは俳句と付き合っていけそうだ、という気がします。
満田春日 Haruhi Mitsuta
昭和30年4月19日川崎市生れ。
昭和58年「海」入会。
平成14年「ゆう」入会、田中裕明に師事。
平成16年第五回「ゆう俳句賞」受賞。
平成17年「ゆう」終刊。
平成18年「はるもにあ」創刊、主宰。
「静かな場所」同人。句集に『瞬』『雪月』(ふらんす堂)
山口昭男:裕明俳句の広がり
シンポジウムで話すことを事前に用意はしていませんでした。ただ、裕明さんの出会いとなった「青」の鍛錬会については話そうと思っていたので、「青」を二冊用意して行きました。
今、ここに東京に持って行った「青」があります。鍛錬会での裕明さんの句をもう少し紹介しておきます。
雪舟は多くのこらず法師蝉
枝紅葉なるほど大き蜘蛛のゐて
蝉とぶを見てむらさきを思ふかな
秋風に卜居の一詩たよりして
このような句を俳句始めてすぐの青年が見たのですから、その驚きはわかっていただけることでしょう。そのことをまず話そうと思ったこと。この「青」の次の号に
雪舟は多くのこらず秋螢
となって、次号の雑詠の巻頭に登場した驚きもまた知らせたかったということで、話をしました。
このシンポジウムの中で、藤田哲史さんの質問で四ツ谷さんが答えられたことが一番心に残っています。それは、
「『詩情』についてさらに深く考えを聞かせてください。」ということに対して「さっき現象学の話をしたように、普段見ているものとは違う形を発見する、本当の形を発見するということが詩情になるのではないでしょうか」
ということです。裕明さんは、絶えず「詩情」ということを口に出されていました。それがどのようなものかは、俳句を通して理解してきたつもりでしたが、まだまだ私の中ではぐらついていましたので、この言葉で少し納得することができました。
存分に話ができたという安堵感と、田中裕明の俳句がこんなに愛され広がっているのだという嬉しさで、帰りの新幹線の中で心地よい想いに浸ることができました。
山口昭男 Akio YAMAGUCHI
昭和30年神戸に生まれる。
昭和55年「青」に入会。「青」同人。
平成12年「ゆう」入会。編集担当。
平成13年句集「書信」上梓。
平成22年1月より俳句結社『秋草』を立ち上げ、主宰。同人誌「静かな場所」所属。
感想

(c)FURANSUDO
安藤恭子:田中裕明「夜の形式」の歴史的文脈とは何か
「夜の形式」とは、もちろん文字通りの「夜」のことではない。<形式>としてそれが成立するためには、その<形式>に既存の形式ないしは様式と一線を画する特徴が認められなければならない。さらに、その特徴がある量をもって歴史的文脈のなかに登場してこなければ、人はそれを<形式>として認定することはない。
だからこそ、「夜の形式」とは何かを説明しようとして、田中裕明は「印象派」や「バロック」を引き合いに出す。そうした既存の<形式>として質・量を認定されているものと対置することでしか、<形式>として認定されていない未だ見ぬものを立ち上げることができないからである。「いま手にしているのは夜の形式ではない」という末尾は、その意味においてきわめて野心的な一文であると言えるだろう。説明の途上で、対置するものとして引き合いに出していた「バロック」を「夜の形式」の側に引き入れてその対立軸を曖昧にしてしまうのも、未だ見ぬ、だからこその可能性を単純な線引きによって矮小化したくないからであり、そのための「あいまいさ」を言うために、あからさまに谷崎潤一郎「陰影礼賛」を引用しつつ、その作者名・タイトルを思い出せないからではなく、わざとそれらを記さないという徹底さによって、<徒然なる思考>すなわち<途上なるがゆえの可能性>を手放さなかったのである。
四ッ谷龍氏のご講演はたいへん意欲的なものであり、田中裕明がレトリカルに回避した「夜の形式」の内実を明らかにしようとするものであった。その方法は、対置された「昼の形式」に分類される具体的な事例(印象派の絵画、バロック音楽など)から、「夜の形式」に分類されると考えられる具体的な事例(クレー、ルドンの絵画、バルトーク、ショパンの音楽など)を割り出し、田中が目指していた<形式>の内実を聴衆に示すというものであった。また、「夜の形式」の叙述に関係するものとして現象学、西田哲学を仮定し、田中の創作の思想的基盤を明らかにしようとした。
このご講演に関して、大きく言って四つの疑問がある。まずは、書き出してみたい。
- 具体的に挙げられた創作の事例には、それぞれの歴史的文脈がある。例えば、ショパンのような、いわゆる亡命者として生きざるを得なかった芸術家において、その芸術観は何と対置されていたのか、あるいはバルトークにおけるそれは何なのか。こうした歴史性・個別性が捨象されてしまうことによって、結局は田中裕明の歴史性・個別性は捨象されることになる。<形式>という表現の束を問題にする際、その<形式>の歴史性を問わないと、いきなり<普遍性>という神秘的な結論に陥りやすい。
- [1.]の問題を回避すると、質疑応答で出された「森澄雄による昭和三十年代生まれの俳人への批判を田中はどのように受け止めていたのか」というタイプの質問には答えられない。田中は、戦後の高度成長期が自らの成長期でもあった、良くも悪くも「二十世紀少年」の世代にあたる(筆者も田中と同年生まれ)。田中の思想をかたちづくる教養の中核の一つにフランスを中心に発信された哲学・思想のトピックスがあることは、四谷氏のお話で理解できた。しかし、それはまさに昭和三十年代生まれが青年期に直面した日本の論壇のトピックスである。田中裕明を批評する座標は、そうした歴史的文脈をとらえつつ、トピックスであったいわゆるWestern thinkingを相対化するところに築く必要があるのではないか。
- [1.][2.]の疑問が頭に浮かぶと、「夜」と「昼」の対置の図式が、近代以降の<明>と<暗>の図式に容易に転化される危険が懸念される。近代文明・文化を<明>、近代文明・文化の光が射さないところ・ものを<暗>とする図式は、近代合理主義・功利主義を批判する多くの芸術家を<暗>すなわち「夜」の側に呼び込んだ。四谷氏が挙げた「西洋世紀末芸術」とその流れはまさにこうした文脈にあり、その具体例は枚挙のいとまがない。そうした意味においては、田中裕明の「夜の形式」はけっして目新しいものではないのである。だからこそ、西洋の芸術思潮を骨の髄まで染みこませた上で、それを逆手にとった谷崎純一郎「陰影礼賛」を引用することが、どのような位相で意味をもっているかが問題になる。
- 四ッ谷氏が「夜の形式」を俳句観に敷衍する際、「昼の形式」として「写生」を挙げていたが、「写生」をそのように矮小化・一元化していいものなのか。これについて述べる紙幅はないが、ロマンチシズムの世界観を相対化するものとして「写生」を再評価する視点が散文の批評の分野にはあることなども視野に入れて、俳句の側から現代の「写生」を論じることが、これからは必要ではないか。「現象学的還元」も、四谷氏が挙げなかった「異化効果」も、「写生」との関連が語られうるであろう。もちろん、田中が「写生」をどのようにとらえていたかは、別の話である。
以上、思いつくままに疑問点を記した。四ッ谷氏のご講演から刺激を受けて、考えなければならないことがいかに多いかを思い知らされたわけである。一九八二年、田中裕明によって書かれた「夜の形式」から、われわれはずいぶん遠くにきてしまった。田中によって構想された未だ見ぬ<形式>の可能性、あるいは、未だ見ぬ<形式>を構想してしまう田中の未完=<途上の可能性>について、その歴史的文脈を現在において見極めつつ、われわれが次なる一歩を構想するには、まだ時間が必要なようである。
安藤恭子 Kyoko ANDO
1959年東京生まれ。1990年作句をはじめ、石田勝彦に師事。1993年から「泉」に所属し、綾部仁喜に選・指導を受ける。1996年『宮沢賢治 <力>の構造』(朝文社)により日本児童文学学会奨励賞受賞。2004年「椋」に入会し、石田郷子に師事。句集『朝餐』(2007)刊。大妻女子大学短期大学部准教授。
井越芳子:見えるように
俳句と本気で向き合うようになったと思える十年を振り返るとき、まるで失語症のように俳句に縛られていると感じながら、しばしば立ち止まったことを思う。そんな時に手にする作家の一人が田中裕明さんであった。不勉強で恥ずかしいのだが、氏の句集の隅から隅までを読むということではなく、鞄の中に一日持ち歩きぱらぱらと拾い読みをした。それだけで、いつの間にか、忘れていた大切なことをとりもどせたような気がしたのだ。
今回のシンポジウム「夜の形式」は、私の中で漠然としていたことが、氏の友人である四ツ谷龍氏の明晰な言葉で語られた。私がたびたび氏の俳句を手にしながら初心にかえることができた理由を教えられた時間となった。
「非定型的、非建築構造的、見えないものをかたちにする、内発的な光」。これらのキーワードによりクリアになっていく。中でも一番印象に残ったのは、次のクレーの言葉であった。「芸術の本質は、見えるものをそのまま再現するのではなく、見えるようにすることにある」というもの。四ッ谷氏はさらに「わかる俳句は、俳句の本質からいちばん遠い俳句で、芸術の本質は、目に見えないもの、まだどんな形かわかっていないものを表すことにある。」と述べた。
俳句を作るとき、目を凝らして見ようとしていたのは、眼前にあるものの向こう側にある見えないものであったと思った。そういえば、裕明氏の俳句は、限りなく低く、そして深深と屈んでいる。見えるまで屈んでいる。息をとめて水中深く潜ってゆく。ものの見えた瞬間、深深とかがんでいたところから一気に掴みとっている何かがある。深くて広い知識の中で、そのことが自然に身についている。
小鳥来るここに静かな場所がある
この「静かな場所」は裕明氏そのもののようでもある。一見、甘やかに見える句だが、この「静かな場所」は、怖ろしく孤独なところ。だから、己を響きだすことのできるひとりのひとりの安らぎの場所なのだと思う。
井越芳子 Yoshiko IGOSHI
1958年東京生。「青山」同人。句集『木の匙』。
平成20年句集『鳥の重さ』により第31回俳人協会新人賞受賞。
黒瀬珂瀾:夜の明るさについて
裕明俳句が放つ「命」を、まぶしく仰ぐことがある。「遊ぶ日と決めて朝から小鳥来る」「小鳥来るここに静かな場所がある」は、まばゆい。命がここにある、その一瞬をまっすぐに見つめているようだ。だがそれは、情念や血潮のたぎりなどとは、まったく違う。きっと、私性に特化し、写生においても寄物沈思を重んじる短歌の方が、「暗い」気がする。
1月24日、四ッ谷さんの講演。「夜の形式」が「昼の形式」と対比される形で語られたからか、抽象性と具体性、不可視と可視など、合理的な二項対立に納めたい誘惑にかられた。でも、そこを押しとどめる、裕明さんの俳句の「明るさ」も、四ッ谷さんは説き明かしていた。「おのづから人は向きあひ夜の長し」「空へゆく階段のなし稲の花」。どちらも、明るい、と僕は思う。暗さに対比される陽光の明るさの話ではない。今この風景を見た、自分自身を見つめ直す視線の明るさがある。四ッ谷さんが言った「内発的な光」を違う視点から考え直すと、そうならないだろうか。
「昼の形式」が、対象の輪郭を見極めることだとすれば、「夜の形式」とは、対象と自分がお互いに見つめあうことだと思う。そしておそらく、「夜の形式」は「昼の形式」を排除することで成り立つのではなく、「昼の形式」を飲み込むことで成り立つのだろう。四ッ谷さんのお話を聴きながらそんなふうに考えていた。「夜の形式」は決して、暗いばかりの形式ではない。
冒頭に挙げた小鳥の句が、なぜまばゆいのか。それは、小鳥の輪郭ではなく、小鳥の中の小さな明かりを詠んだ句だからなのだと、ようやくわかった。そして、そのほのかな命を通して「わたし」は、小鳥の視線の先にいる「わたし」を見ている。
作品を誌面で拝見するだけだった。2003年の正月、思いきって歌集をお贈りした。しばらくして、お手紙と「ゆう」をお送りくださった。同じ大阪にいるのだから、いつかお会いできると思って、疑わなかった。
黒瀬珂瀾 Karan KUROSE
1977年、大阪生まれ。春日井建に師事。「白い鳥」、「中部短歌会」を経て、現在、「未来」、[sai]、「鱧と水仙」に参加。
歌集に『黒耀宮』(第11回ながらみ書房出版賞)、『空庭』。他著書に『街角の歌』。現代歌人協会会員。
駒木根淳子:「絆」を考えた日
若い頃の田中さんが書かれた「夜の形式」という文章をテキストに、裕明俳句の本質を解き明かそうとする四谷龍さんの考察から「文学としての俳句」を再確認した。この「文学としての俳句」という言葉は私の参加する同人誌「麟」の裏表紙に記した一行なのだが、実際の俳句の現場では石田波郷の「俳句は文学ではない」という言葉が何を示唆するのか考えることのほうが圧倒的に多い。
そもそも裕明俳句が新古典派(日本の古典文学や美意識を連想しがちだ)と分類されることに釈然としない思いを抱いていたから、この優れた俳人の文化的背景を西洋の哲学や芸術で解き明かそうとする試みは新鮮であり、蒙を啓かれた。しかも、若き日からともに句作し論議を戦わせた友人によってなされた考察には、故人への強い思いがにじむ。できれば次回は、実際に具体的な裕明俳句をあげて、詳しい検証を拝聴したい。
第二部のシンポジウムを聞き、人間関係が希薄な時代のアンチテーゼとしての、「俳縁」というよりさらに強いもの、たとえば「絆」のような言葉が浮かんだ。各人の田中さんとの思い出を通して、尊敬する俳人を胸深く持つ幸せが伝わってきた。とりわけ夫人の森賀まりさんは俳句をきっかけとした出会いから、田中さんの本棚の中身まで、身近ゆえに知る逸話を思慮深く穏やかに、ときにユーモアを交えて話された。裕明さんは確かにあの若さで重い病と闘い、たくさんの悔しい思いをなさっただろう。しかし、一方で誤解を恐れずに言えば、こんなに聡明で冷静で、それでいて明るく情の深い女性に最期を看取られ、男性としては幸せな一生だったのではないだろうか。
帰りのエレベーターのなかで高橋睦郎さんが(シンポジウムの「裕明俳句は神に向かって作った」という四谷さんの発言を受けて)「神というのは大袈裟だが、はるかなものに向って確かに句作していた」と(そんな意味の言葉を)呟かれた。乗り合わせた者は『友達の作り方』の著作を持つ人物の含蓄ある言葉に聞き入り、やるせない喪失感と鎮魂の心を共有した。「絆」を考えた一日にふさわしい締めくくりになった。
駒木根淳子 Junko KOMAKINE
1952(昭27)年、福島県いわき市生まれ。
1992(平4)年「青山」入会、2002(平14)年、同退会。
2005(平17)年 俳句同人誌「麟」創刊に参加。編集を担当する
第4回朝日俳句新人賞準賞受賞
俳人協会会員
酒井佐忠:アートとしての俳句論
「夜の形式」と聞いた時、体内に何かが弾ける想いがした。長くくすぶっていた熾火が、突然小さな白い炎をあげる。そんなときめきがあった。「夜の形式」とは何か。そう問うことは、私たちが日ごろ感受する言葉の輝き、美の正体、あるべき詩の姿、思考の揺らめき、感動の在り処などを確認することにほかならいことに気づく。
田中裕明が「夜の形式」と題する短文を書いたのは二十二歳のときだという。恐らく彼もこの形式についてはっきりとした概念で語ったのではなさそうだ。「夜はしだいに明けてゆくのだけれども、時間がそちらの方向だけに流れていると思うのはおかしなこと」と書いている。そのように「夜の形式」は、単純な時間の経過とは一致しない、心の揺らぎの中の時間と、光と影が交錯するようなボーダーレスな世界から誕生することに、ただ漠然と気づいていたのだと思う。
四ツ谷龍氏もまた、芸術形式としてのこの言葉にこだわった。その謎を解くことが田中の詩(俳句)の解明に役立つと考えた。哲学、美学、音楽、建築、さらに現象学まで幅広く考察し「夜の形式」は何かを問うた。それは1非定型的2非建築構造的3光の内発性4本質的直観ーなどを特長とした揺らめきと重層的な眼差しがもたらすものであった。
「夜の音楽」としてショパンのノクターン(夜想曲)を例示したとき、心は揺らめいた。ショパンは曲想の変化が激しく、いわば非建築構造的な夜の音楽。ベートーベンの「運命」は固定的な通奏低音による昼の音楽で、俳句では「彎曲し火傷し爆心地のマラソン」(金子兜太)に当たるという指摘にひどく納得した。実は私は、ショパンの夜想曲を聴きながら原稿を書くことが多いからだ。この論が直ちに田中裕明の詩性の解明につながるかどうかは疑問もあるが、少なくとも俳句形式を他の芸術と同じ舞台で論じ、俳句を「アート形式」として捉えたことを評価したい。
酒井佐忠 Suketada SAKAI
文芸ジャーナリスト。神奈川県生まれ。元毎日新聞専門編集委員。現代詩歌の取材・執筆をする。
著書に詩歌エッセイ『風のことのは』『今朝のうた第一集・第二集』など。
榮 猿丸:裕明俳句の特質
田中裕明による「夜の形式」と題された、芸術に関する小さなテクスト。しかしそこには最後まで「夜の形式」とは何かが明確に示されない。四ツ谷氏は、この謎めいたテクストを手がかりに、裕明俳句における「夜の形式」とは何かを考察する。フッサールの現象学を参照しつつ、近現代の芸術作品を挙げながら「昼の形式」と「夜の形式」を対比し、各々の特徴を明らかにした上で、裕明俳句は「夜の形式」の芸術のもつ特質を備えている、と結論づける。その論旨は明解で鮮やかだ。
しかしそれが明解であればあるほど、われわれは再びテクストへと立ち返る必要があるだろう。たとえば、テクストの前段で、夜の形式に対する昼の形式として、印象派の絵やバロック音楽が挙げられており、四ツ谷氏はここから芸術における昼の形式というものを例示していくのだが、テクストの後段では、「夜の形式というのはかなり複雑なもので、それは時間と非常にふかい関わりをもっている。だからさっき昼の形式としてあげたバロック音楽も、深夜ひとり机にむかって目瞑る男が書いたと考えることができる」と述べる。つまり、裕明は、前段で昼の形式と夜の形式という対比を自ら提示しておきながら、後段でその対比を無効化しているようにみえる。
そうすると、四ツ谷氏が「夜の形式」への方法として着目したフッサールの現象学的還元は、近代絵画史からみれば、むしろ昼の形式とされた印象派の「純粋視覚」こそふさわしいのではないかという疑念も生じてくる。
また、「時間」が主題化されなかったことも疑問に残る。先に引用したように、夜の形式は「時間と非常にふかい関わりをもっている」。そして最も重要と思われる箇所は、谷崎潤一郎の「陰翳礼賛」に触れたあとの、「日本の座敷は午すぎの外の光を障子からとりいれてはじめて、その明暗のあいまいさを時間の久しさに転化させるのだけれども、夜の形式と言ってよいかもしれない」という一文ではないだろうか。「明暗のあいまいさを時間の久しさに転化させる」形式。こうした部分にむしろ、裕明俳句の特質を思うのである。
榮 猿丸 Sarumaru SAKAE
1968年東京生まれ。2000年、澤俳句会入会、小澤實に師事。2004年、澤新人賞。
「澤」同人、俳人協会会員。
手塚敦史:ひとの膜
僕にはこれといって語るに足る実生活がない。粒子のように淡い時間の中を、生きている。ものすごく極端なことを述べていて恥ずかしいので、もう少し判断をするのは保留にしていたい。ただ先日の四ツ谷龍氏の講演「『夜の形式』とは何か」を聴き感じられるのは、話題の中心になっていた田中裕明氏と、その出会って来た人たちに対する強い憧憬の気持ちであったのだ。その羨望のまなざしだけがイベントの後までも残っていた。
愛惜の品を披露するように田中氏の俳句について丁寧に焦点を絞り語って行く四ツ谷氏の表情は、とても活き活きとしていた。それから会の第二部では、田中氏と親しかった方たちが次々に登場し、田中氏との思い出やその俳句に対する批評について自由に聴かせてくれた。さらに会が終わった後の酒の席では、偶然自分の前に坐っていた森賀まりさんとそのお姉さんとお話する機会を得ることができた。俳句のイベントに顔を出したのはこれで二度目であったが、この日ほど幸福な気配を自分の背後に受け取れたのは初めてかもしれない。
この日の何が幸福だったのか、後で考えてみた。田中氏と縁のある方々が、あの場に集まったのが見えたということ。浮世のしがらみも何も関係なく、その作品と人柄を現在気ままに伝え合えるということ。その場にできた、ひとの膜が一等とうとく存在していたということ。それらを前に、僕には何も語れなかった。おそらく語られるべきことの真っ只中にいるから、何も語らないのだ。しかし、自分とは距離のある俳句の方たちとお会いすることが出来、語らずとも伝わって来るものが確かにあった。それは人の住む時の在り処に触れることができた感覚、または時の背後に映る水面に波紋を残し、主体が反照して行ってしまう意識でもあった。何はともあれ、こちらも埋没して今は見えない日々を過ごしていてよいのだ、という確信を持てた。不意に水紋が生じてしまう、とは、別に特別なことではなかったようだ。ただ、その瞬間が生活する中にあることを悦びたかった。
手塚敦史 Atsushi TEZUKA
1981年8月29日甲府市生まれ。
2004年、『詩日記』(ふらんす堂)。2006年、『数奇な木立ち』(思潮社)。共著に『詩のリレー』(ふらんす堂)。
鴇田智哉:人に何かを言わしめる人
第一部の講演中、あ、と思ったことがあった。スライドで、クレーの「金色の魚」が映し出されたときだ。画面まんなかにいる金色の魚が、田中裕明さんに似ているのだ。私は田中裕明さんを、写真でしか見たことがない。が、よく似ている。内側から発光してくる感じ。クレーの絵は、クレー本人また、講演で四ッ谷龍さんが説明してくれたように、確かに内側から発光していると、私も思う。そして、写真で見る田中裕明さんの姿は、表情と、目のためかと思うが、内側から光っているように私は思うのだ。
この印象、ひらめきは、私の中で一つの考えとなっていった。それは、田中裕明さんは光源を自らの内にもっており、その光源が作品を生んだし、光源が人柄として、人を引きつけもした、そういうことだったのではないだろうかという考えである。
作品ということで言えば、私は、田中裕明の幾つかの作品に引かれているが、それは、彼の言葉に独特の、微妙な調和に引かれているのである。この微妙な調和は、光源としての田中裕明がもたらすものであろう。
また、彼の人柄が人を引きつけた、ということは、第二部のパネルディスカッションにおいて、とてもよくわかった。だれもが田中裕明という人を今でも大切に思い、彼について語りたいと感じているということが伝わってきたのである。亡くなってなお、人に何かを言わしめる。光源は生きているのだなあと。
講演は、四ッ谷龍さんのものの見方に触れることができて面白かった。また、バルトークのピアノ曲などうっとりと聞いてしまい、私としては、無責任な聴衆として、のどかに楽しく参加できた。そんな中、私にとっての最大の収穫は、田中裕明「夜の形式」という文脈の中で、クレーの絵を見せてくれたことだったと、今、思うのである。
鴇田智哉 Tomoya TOKITA
1969年、木更津に生まれる。
1996年、「魚座」入会。
2001年、俳句研究賞受賞。
2005年、俳人協会新人賞受賞。
2006年、「魚座」終刊、「雲」入会。
「雲」編集長。句集に『こゑふたつ』がある。
藤田哲史:不思議な時間
2010年1月24日のことについて書きたかったのに、いつのまにか書くのがむずかしくなってしまった。それほどその日の勉強会は、不思議な時間だったということ。
そもそも四ツ谷龍さんが「夜の形式」を語りはじめるときに、「これは私の解釈でしかありません」と発言したときから、すでに何か不思議なものがその場所に降りていたのだけれど、それは森賀まりさんにしてもそうで、彼女もていねいに裕明とのエピソードを一つずつ語るのだが、不思議なことにいくつエピソードを話してもそれらは決して帰納的思考に結びつかず、つまり結局のところいつまでも裕明の像は闇の中にあって、はっきりとそのおもかげを見せてくれることはなかった。
どうやら(かなしいことに)勉強会がはじまるずっと前から「論理的思考をもって田中裕明を解釈するというのは無謀な行為である」ということを、身近な人ほどはっきりと認識していたらしく、いま、先に書いた「不思議な時間」を無理矢理言い換えるなら、その時間は「詩を紡ぐための時間」であって、オベンキョウの時間などではなかった、ということ。実際、四ツ谷さんが「昼の形式」として示した芸術作品ごとの間にある大きな隔たりも、詩的飛躍としての隔たりだったと言える。何より、「わかりやすいもののなかに詩はない」という四ッ谷さんの言葉こそ、その時間の核心だったろう。
そのような、詩でもってしか裕明を説明できなかった時間を、散文で書き起こすというのはどだい無理な話で、どんなに裕明を解釈しようとしても、最終的には彼の詩のなかに溺れてしまう。
と、いう結論。(になっていない。)
あるいは、詩を蒸留しつづけることが詩人の仕事なら、田中裕明を語り終えるにはまだ早くて、彼以後の詩は、彼の朦朧体のスタイルの向こうにある気がするけど。ちがうかな。だからこそ、全てはこれから、なのだ。
藤田哲史 Satoshi Fujita
1987年、三重県生まれ。2007年、小澤實に師事。
高校二年生のころ、「初雪の二十六万色を知る」に衝撃を受けたのを覚えていて、だから、じぶんの俳句のルーツは田中裕明です。
リンク
<夜の形式>にかかわるサイトのリンクを貼っていきます。
[3/25]関 悦史さんが「豈ウイークリー」にて「田中裕明「童子の夢」50句」と題して田中裕明の俳句について書かれています。
[3/25]藤田哲史さんが「豈ウイークリー」にて「セレクション俳人を読む1 『田中裕明集』 制御の内外」と題して田中裕明の俳句について書かれています。
[2/7]生駒大祐さんが、「週刊俳句 Haiku Weekly」にて、1月24日に行われた『夜の形式』第二部についての詳細なレポートを書かれています。
[1/31]俳人の上田信治さんが、「週刊俳句 Haiku Weekly」にて、1月24日に行われた『夜の形式』詳細なレポートを書かれています。