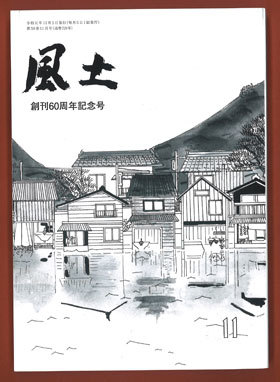写生って何だろうということを常々考えておりました。
「風土」は波郷、石川桂郎とつながっていくわけですが、そのなかで写生って大事だよってことがあり、わたしなり写生のことを考えました。最初は正岡子規の俳諧大要を読んで自分なりにおおまかに写生というものを掴んでみたのです。その過程で波多野爽波の俳句に巡り逢ったわけです。カルチュアショックを受けました。そのような中でわたしなりのとらえ方ですが、まず表現技術の一つであるということ、もう一つは態度であるということ、何が何でも頑張って対象と向き合って写生をするぞという態度であるということです。精神論でもないです。それを理論化してくれたのが青木亮人の『その眼、俳人につき』の本でした。その本によってこれが写生の原型であるということがわかったんです。それは何かというと、
赤い椿白い椿と落ちにけり 河東碧梧桐
これが写生であると。なぜそうかと言うと、その頃の明治期の俳句はひねりが入っているわけですね。それが江戸期からずっと続いてきた俳句の表現技術の一つであるわけです。たとえば、
落ちてから花の数知る椿かな 梅人
「落ちてから」の「から」がひねりなんです。落ちてからはじめてたくさんの椿が花をつけていたことを知ったわけです。この「落ちてから」という読み手側にとっては、「落ちてから」なんだろう。「花の数知る」なんだろう、「椿かな」で立ち止まるわけです。一つの世界を想像するに立ち止まり立ち止まりしてはじめて「花の数知るつばきかな」いうのがわかる。ところが、河東碧梧桐の「赤い椿白い椿と落ちにけり」では、まず「赤い椿」で赤い椿を想像する、「白い椿」で白い椿を想像する、「と落ちにけり」でそれが落ちるところを想像するということで、読む速度と想像する速度が同時でブレがないんです。これが写生で一番大事なところなんです。眼の前に見えるわけですよね、赤い椿が落ちるのが、そういうように想像する世界と読む世界がほとんどおんなじであるということですね。また、そこで大事なのは見えるように描けるということなんですよね。これを正岡子規は提唱したわけです。その頃の明治の俳人たちは子規の写生をなんだこれは只事俳句ではないか、と馬鹿にしたわけですが。この子規の写生がその後虚子に引き継がれていわゆる写生表現の充実となったわけです。
桐一葉日当たりながら落ちにけり 虚子
これもまた落ちるんですが、「桐一葉」は中国から来ておりそれで秋を知るということなんですが、そこで虚子はどこにアクセントをつけたかというと、「日当たりながら」ですね。「日当たりながら」というところで、わたしたちは、その桐の葉が日に当たりながら落ちてゆくさまを想像できる、さっきもいいましたが、読む速度と想像する速度がほとんど同じです。で、非常に印象が明瞭です。これが写生の一番大事なところです。
この後山口誓子の、
夏草に汽罐車の車輪来て止る 誓子
映画の動きを取り入れた写生の方法があります。誓子につづき高野素十が同じような手法で、かれは新潟県の農村へずっと通っていろんな俳句をつくるんですが、そこで素十は誓子と同じように動く映像を俳句に定着させた、たとえば、
翅割つててんとう虫の飛びいづる 素十
有名な句ですが、まさにこれから飛び立とうとするテントウ虫を表現しているわけです。これ以降、いろんな写生表現が展開されていくわけです。たとえば、石川桂郎が、
雨まじりゆき降る中の初蛙 桂郎
という句をつくってゆくわけですが、これを秋桜子さんに見せたところ秋桜子さんが、なんだこれ、嘘だろうと言っていたなどということですが、大事なことは、初めて蛙を鳴いたときは雨交じりの雪だったよ、ということを率直に表現しているわけです。このことから、写生でもう一つ大事なことは、「ありのまま」ということがもうひとつあるわけですよね。これも写生表現のひとつの展開であると思います。神蔵器に、
鮭を追ふささら青竹水打つて 器
これは東北の鮭をとるときの吟行句なんですけど、竹をもって水面を叩きながら鮭を追っていくわけですが、その様子をそのまま写生したわけです。このように写生はいろいろとあるわけですが、一番大事なのは読む速度と想像する世界が同じであるということです。そのように伝えるということが大事、もうひとつ見える俳句をつくるということ、読み手に伝わる、想像させる、見えるように想像させる、あるいは肌触りがあるようにつくるということが大事です。わたしは句会でそういう句を採ります。先ほどもうしたように「写生」の基本は明治期に正岡子規が提唱した碧梧桐の「赤い椿白い椿と落ちにけり」が原型ではないかと思っております。
それと、もうひとつ写生のなかで大事なこと、さきほど「ありのまま」と言いましたけれど、「ありのまま」を追求するとこれはですね、ある俳人が言いましたけれど、「グロテスクにぶつかる」というのです。
自分のなかで勝手に世界をつくらないということですね、写生を追求していくとあるわけですよ、じいっと見てると、えっ、なんでこんなことがということもあるわけですよ、それを恐れずに表現するということも大事。それともう一つ大事なことは「移ろい」ということ、印象明瞭は「瞬間」ということにつながりますが、本当は移ろっていくんですよね、もののありようというのは。高野素十にこういう句があります。
秋水に蝶のごとくに花藻かな 素十
というのがありますが、「秋水」は秋の水、「蝶」は比喩ですが、春、「花藻」というのは「藻の花」のことでと季節は夏なんです。で素十は、この句を生んだわけですが、この句には三つも季語が入っている。でもこれは梅花藻みたいにいっぱい咲いているときは、蝶のようには見えない、秋になって花の数が少なくなって、白い花があちこちで揺れ動いているわけです、それはまさに蝶が舞っているなという、「秋水」が季語ですが、そのなかで終わりを告げようとしている「花藻」、こういう「移ろい」を捉えることも写生においては大事だと思います。ですから、「季重り」を恐れずに作ってみましょう。